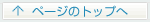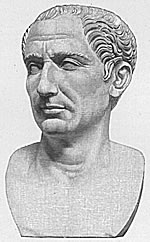���[�}�j�_�W - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

�u�Ñネ�[�}�̃C���y���E���ɂ��āv
�h�Dimperium�̋N���E�E�\
�@�@�uimperium�v�C���C���D
1�D���߁C�w�}�@2�D���́@3�D�x�z�C�����@�ipl.�j
�鉤�Ƃ��Ă̍s�ׁC�匠�҂̖��߁C�N���@4�D�E���C5�D�����C�R���C�w�����C���ߌ��@6�D�����̐E���@7�D��l�C�����@8�D�w�����C�i�ߊ��@9�D���C���ƁC�̓y
�@�����i�����Ёw���a���T�x�j��imperium�Ƃ������t���Ђ��ƁC���̂悤�ɖ����Ƃ��Ă͈ٗ�ɑ����̈Ӗ�������ł���B���̂��Ƃ����������̂����Cimperium�Ƃ͒ʏ�̗��j�T�����ł悭���|����u�ō��w�����v�Ƃ��C�u���ߌ��v�ȂǂƂ����P���ȊT�O�ł͕\���ł��Ȃ��C���Ɠ��ȈӖ������������Ă������t�ł���B���ꂩ��C���[�}�̐����v�z��[�I�ɓ����Â����C�uimperium�v�Ƃ����T�O�ɂ��čl���Ă䂫�����B
�@imperium�̓��[�}�����̌��n���������̂̒��ō��J�̒��ł���u���v�irex�j���������C�����I�E�@���I�i��p�I�j�ȈӖ��Ől�����x�z���C�����̂�폟�ɓ����C�x�z�҂ɓ��݂��錠�͂ł���ƍl�����Ă����B���̌��͂̑��̂ł���uimperium�v�������N���Ɏ����Ƃ́Cimperium�̏d�v�ȗv�f�̂ЂƂł���R����̑��w���������������Ă������Ƃ���ؖ��ł���B���Ƃ��C���͐푈���s�̂��߃��[�}�s�O�֏o��Ƃ��ɁCimperium����ԂɂȂ郍�[�}�Ɂu��s�v���G�g���v�ipraetor urbi�j���c���C�M���҂͂̂��̂��܂ʼn��̕���������K�킵�ł������B�܂���q���邪�C�M���҂ɂ��Ă̓J�G�T���̍��܂Łu���肢���v�iauscipium,auscipia�j�������Ȃ����̂͊M�������s�Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁC�M���҂͌R�w�����ƂƂ��ɐ_���Ƃ��Ă̐��i�������������Ă������Ƃ�������B��͂�imperium�̋N���́u���v�ɂ������悤�ł���B
�@imperium���ے�����t�@�X�P�[�X�ifasces ���̂܂��ɖ_�����˂����́C�R���X���̐E���̏ے��j�̓G�g�����A�s�s���Ƃ̎ilauch(u�jme�j�����E�^�D�̑匠���ے����邽�߂Ɏ��������̂��N���ł��邪�C"imperium"�̍L�͂ȊT�O�́C�ǂ���烍�[�}�ŗL�̂��̂炵���B
�@imperium�̊T�O���̂��ω������邪�C���a�������̍ł��u�W���I�v��imperium�̌`�Ԃɂ��čl���Ă݂�B
�@"imperium"�̑�܂��ȈӖ��́C�O�߂ɋ������Ƃ���ł��邪�C��`����Ȃ�C�u��ΓI�E�Œ�I�ȈӖ��Ŋm��I�Ȏ��㌠�C���O�㓯��̂��̂ł���i�����Ƃ��āj�e�E���ɂ͕����ꂸ�C�����͒i�K�t�����Ȃ������B���Ȃ킿�C���Ǝ́C�S�Ă����閽�ߌ��C���̌����S�́v�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B����ɑ��āC������E�ҁimagistratus�j�������ƌ��͂��u�E�������v�ipotestas�j�ł���Cimperium�Ƃ͂͂������ʂ������̂ł������B���Ƃ��C�Ď@���icensor�j�͔��Ȗ��_�̔��Ȃ�������E�ł��������C�ˌ������̂悤�Ȍ��肳�ꂽ�C�����s�Ȃ�potestas�͎��������Cimperium�͎����Ȃ������B
�@����imperium�ێ��҂��ʂ������Ƃ̂ł����X�̐E�\�ɂ��čl���Ă݂�B
�@���ɁC�O�߂ł��G�ꂽ�悤�ɁCimperium�ێ��҂͐肢�E�]���E��[���E�_�a���c�Ȃǁu���v�����璼�ڎp�����ƌ�����L�͂ȏ@���I�������������B���ł��u���肢�v�iauscipium�j�̌����͏d�v�ł������B���[�}�ł͌×���蒹�̔�ѕ��E�a�̂��ݕ��Ȃǂō����̋g����肤�K��������B���[�}�̌����҂Ƃ���郍�����X�iRomulus�j���o�q�̒탌���X�iRemus�j�ɏ������C���ƂȂ����̂����́u���肢�v�ɂ��Ƃ̓`�������邪�C���̂��Ƃ�������́u���肢�v�����[�}�l�ɂƂ��Ă����ɏd�v�Ȃ��̂ł��������Ƃ�������B�������imperium��auscipium�ł͂Ȃ����C�����u���肢�v����imperium�̏d�v�ȗv�f�ł��������Ƃ͊m���Ȃ悤�ł���B
�@���ɁCimperium�̌R���I�����ɂ��čl�@����B���Ɗ�}�̑厖�ł���펞�����C���Ƒ匠�Ƃ��Ă�imperium�̎p���[�I�Ɍ����Ă���B���[�}�̌��E�҂͌R���Ґ��i�����j���E�R�����w�����E�i�����͍������Z�C�������j�����������C���[�}�I���E�Ҍ����ς́u������́v�Ƃ����l�����ł���̂ŁC����͓��R�̂��Ƃł��낤�B�����ɕt�����錠���Ƃ��ẮC�M�������s�Ȃ������C�C���y���[�g���iimperator�j�̏̍���тт錠���C�O���Ɓu�K���ɂ��čS���͂����v����S�l���̖��ɂ���Ē������錠�����������B�i���z���ƍu�a�������̌��茠�͖{���͖���ɑ�������̂ł��������Cimperium�ێ��҂͌��V�@�̏��F�Ă�����s�����Ƃ��ł����B�j
�@��O�ɁC�����Ɋւ��鎖�����܂Ƃ߂Ă݂�B
�@�܂�����Ƃ̊W�Ɋւ��ẮCimperium�ێ��҂���������W������Ɍ��c�̂��߂̒�Ă����錠�����������B�܂��C���V�@�ɑ��Ă��قړ��l�̌�����L�����B
�@�i�@�W�ł́C�i�ׂ��Ǘ����C���i�ɑ��Ď��l�Ƃ��Ă̒��َ҂ł���u�R���l�v���߂��Bimperium�̂��̔C���ɂ͓����������iconsul�j�C���Ŗ@�����ipraetor�j�����������B�i��II�͎Q�Ɓj�܂��C����imperium�ێ��҂́C���ƌ��͂Ǝ���̖��߂d�����邽�߂��u�������v�iexercitio�܂���coercitio�j���������B�i�������C�d��Ȃ��̂Ɋւ��Ắu��i���v�iprovocatio�j������C���̌��̗͂��p�ɂ͎��~�߂��������Ă����B�j
�@���̑��C�����I�Ȍ����ł͂��邪imperium�ێ��҂͎��Ȃ̕⍲���E�����Ȃǂ�����w�����C�R���ʂł͈��́u�������v��L���鏫�Z�E���m�����w�������B�܂��C������imperium�s�g�̌����𑼎҂Ɉϑ��imandare�j���邱�Ƃ��\�ł������B
�@���̑��Cimperium�ɕt�����錠���Ƃ��ẮC�l�X�ȉh�_����C�t�@�X�P�[�X�Ȃǂ̐E���W����тт錠���Ȃǂ����邪�C�����ł͏ڂ����͐G��Ȃ��B
�@���ʁu�������v�Ƃ��u���́v�Ƃ����R���X���́C���[�}������̍ō�����Ɉʒu���C���Ă��u���v�irex�j�̒��ړI��p���ł���ƌ��Ȃ����B���͖{���̓��[�}�B��́u���E�ҁv�i�܂��́u�������vmagistratus�j�ł��������C���̌�K�v�ɉ����Ċe��̌��E�҂��ݒu����邱�ƂɂȂ�B
�@�R���X���͂h�͂ŏq�ׂ�imperium�̏������̂����C���V�@��c�E�I������Ȃǂ̏��W�Ǝ�Ì��C�i���ƎƂ��Đ펞�Ɂj�R���̍ō��w�������������B���̑������S�ʂɂ����ăR���X�����֗^�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�u�R���X���㗝�v�̂��Ƃł���C�R���X���̑㗝�Ƃ��đ��B�����⑮�B�ł̐푈�w���Ȃǂ��s�Ȃ��C���B�ł̓R���X�����l�̍L�͂�imperium��тт��B�v���R���X���ɂ��ẮC�̂��Ƀ|���y�C�E�X��J�G�T���̌������l����ۂɂ�����x���y����B
�@�u�ƍي��v����f�B�N�^�g���͔j�i�̐��i�������Ă������C���炭�̓��[�}�ō����E�Ƃ��čŌÂ̋@�\�������Ă����B�f�B�N�^�g���͍��Ƃ��ُ�Ȋ�@�ɂ��炳�ꂽ�ꍇ�Cimperium�����R���X���ɂ���Ďw���������̂ł���B�ނ͍ō��̌��E������P�Ƃŏ������C�R���X���ł��������ނ�imperium�ɕ������B�f�B�N�^�g���͍ő��6�����̔C�����Ɍ���C�ꎞ�I�Ȃ������Ắu���v�irex�j�̊��S�ɂ��Ė������imperium���Č������B
�@���炩�̗��R�ŃR���X����f�B�N�^�g���̍ō����͂���C�҂ɒ��ڈ����n�����Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�C���V�@�̋M���n�c���̒����炭���т��ŏ��Ԃ����߂āC�C���e�����[�N�X�i���ԉ��j�ꖼ�𗧂Ă��B����́u���v�irex�j�̖��̂����������悤�ɁC���ɌÂ��`�Ԃ������C�܂��Ɂu���v�̍Č��Ƃ��Č�������̂ł������B�ނ̎���imperium�͌R���E�����Ƃ��Ɋ��S�Ȃ��̂ł��������C���̔C����5���ԂɌ����Cimperium�̖{���I�ȍs�g�����u���肢���v���܂߁C�@����̈Ӗ������������C���̖{���͎��̃R���X���̓K�ȑI���ɂ������B���̃C���e�����[�N�X���x�́C�f�B�N�^�g���ƂƂ��ɋ��a�������ł͗�O�I�ȑ��݂ł��������C���ꂾ���Ɍ×���imperium�̎p�𒉎��ɍČ����Ă���ƍl������B
�@�v���G�g���i�@�����j�͂��Ƃ��Ɖ���R���X�����푈�Ȃǂ̂��߂Ƀ��[�}�s�O�֏o��Ƃ��ɁCimperium�����@���郍�[�}�s���Ɏc�����u��s�v���G�g���v�ipraetor
urbi�j�ɗR��������̂ł��邩��C���Rimperium���������B�v���G�g���͗��_�I�ɂ̓R���X���ƑΓ��ł��邪�C���҂���������ꍇ�ɂ̓R���X���ɕ������B�܂��C���̋N�������������悤�ɁC�R���X�������_��S���[�}�̓y��imperium���s�g������̂ɑ����v���G�g���͌���ꂽ�u�E���̈�v�iprovincia�j���ł���imperium���������Ȃ������B�����āC���̐E�����e�Ƃ��ẮC��s�v���G�g���̓��[�}�s���̎i�@�E�s�����s�Ȃ��C���B���̃v���G�g���͒S�����B���ł̌R�w�����E�������E�ٔ����܂ފ��S�������imperium���������B
�@�얯���͐g�̂̐_���s�N���E�~�ό��ȂǗl�X�ȍL�͂Ȍ��͂������Ă͂������C���ꂪ���Ƃ̌��E�ł͂Ȃ��i�얯���́u�����v�������S������j�Ƃ������O����imperium�͎������Ȃ������B�������C���̌얯�������̓A�E�O�X�g�D�X�̌��iprincipatus�j�Ɏ����āC�`��ς���imperium�̒��Ɏ�荞�܂�邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃɂ��Ă͌�q����B
�@���a�����[�}�ɂ͏�q�̂ق��ɁC�Ď@���i�P���\�� censor�j�C���c���i�A�G�f�B���X aedilis�j�Ȃǂ̍��ƌ��E�����������C�ނ�͂��̌���ꂽ�E���䂦���u�E�������v�ipotestas�j�͎������Ă�imperium�͎����Ƃ��ł��Ȃ������
�@imperium�͌��������ɋN�������C��ΓI���㌠�ł��������C�N�����o��ɂ��������ėl�X�Ȑ�������悤�ɂȂ��Ă����B�������L�͂�imperium�̌����Ɣ�r����Ύ��ɑ���Ȃ��������������C���̐��������̓��[�}���a�����W�̏�ŏd�v�ȃe�[�}�ł���ƍl������̂ŁC�����ł͓��Ɉ�͂�݂��čl�@���Ă݂����B
�@imperium�𐧌����鏔���͂̂����ŁC���Ƃ����Ă��ő�̂��̂͌얯�������ł���B�얯���͂��Ă��́u�~�ό��v�iauxilium
ferendi�j�ɂ���Č��E�҂ɑR���Ďs�������C�����iintercessio�j�ɂ���Č��E�҂̐E�����s��W�Q���邱�Ƃ��ł����B����ɂ̂��ɂ́C���́u���ی��v�iveto�j�̓R���X���܂ł������]������悤�ɂȂ����B�ЂƂ̌Ñ㍑�Ƃ��C����ɑ����R��������̑̓��Ɏ����Ă����Ƃ������Ƃ͂���߂ďd�v�Ȃ��ƂŁC���̓_���a�����[�}�̓I���G���g�ꐧ���ƂƂ͖��炩�ɋ�ʂ����B�i���̂��Ƃɂ��ẮC�̂��Ɂwimperium�̕���x����сw���[�}�s�������̂�imperium�x�̏͂ł�����x�l���邱�Ƃɂ���B�j
�@���ɂ��Ƃ���imperium�ɓ��݂��鐧���͂��l����B
�@���a�����ɂ�����imperium�ێ��҂͌����Ƃ��Ďs���ɂ���ēK�@�ȑI���őI�o���ꂽ���̂ł���������C���̕�̂ł��郍�[�}�s���C���Ȃ킿���[�}�s�����i�Ƃ��̎s�����Ɋ܂܂�鏔�����j�ɂ���Ă������̐��������B���̍ł������Ȃ��̂�imperium�ێ��҂́u�������v�iexercitio�j�ɑ���u��i���v�iprovocatio�j�ł������B���̌����ɂ�胍�[�}�s���͌��E�҂��ۂ�⚌Y�⎀�Y�i�̂��ɂ͔����Y���j�ɑ��āC�ЂƂ܂����̎��s���~�����C�������������@�삩����ł̔����邱�Ƃ��ł����B�������C�f�B�N�^�g������ъM���҂̊M���������́C�����Ƃ���imperium�s�g�Ɋւ��ď�i���ɂ�鐧�����Ȃ��������C���ʑi�葱�����s�Ȃ�imperium�ێ��҂ɂ��Ă����l�ł������B
�@�܂��C����͖{���I�ɂ͑��҂�imperium�ɑ��ĉ����鐧���ł͂Ȃ����C�R���X���C�v���G�g���Ȃǂ̂قƂ�ǂ̌��E�҂��������������Ƃ�C���ꂼ�ꂪ���̓�����imperium���K���������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ɉ����ē���imperium�ێ��҂ł����Ă��C���Ƃ��R���X�����v���G�g�����㋉��imperium���������悤�ɁC�㋉���E�҂��������E�҂̎���imperium�𐧌����邱�Ƃ��ł����B
�@�����ЂƂɂ́u�E���̈�v�iprovincia�j�̐��x������B����͕�s�v���G�g����imperium�̓��[�}�s�̈���Ɍ���Ƃ��C���B���iproconsul�j��imperium�͂��̒S�����B�Ɍ���Ƃ��������̂ŁCimperium�ɑ���s�g�̐������������B
�@�܂��������C�E�����ԁi�C���j�ɂ�鐧�����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�h�`III�͂ŏq�ׂĂ���imperium�͂����ς牤�����`���a�������̊T�O�ł������B�������C���a���������C������u�����̈ꐢ�I�v�̎���ɂȂ��imperium�̂�������傫�ȕω��𐋂��邱�ƂƂȂ�B���̏͂ł͂��̕ω������㏇�ɒǂ��Ă݂����B
�@�e�B�x���E�X=�O���b�N�X�iTiberiusSemproniusGracchus�j�̓y�n���v���n�܂����̂͋I���O133�N�̂��Ƃł������B���̉��v�͌��V�@�ێ�h�̍U���ɂ����č��܂��C�e�B�x���E�X�͔ߌ��I�ȍŌ�𐋂��@��B�e�B�x���E�X�́u�얯�������v�ɂ�肱�̉��v�̎��{��ڎw�����̂ł���C���̈Ӗ��Œ���imperium�Ƃ͊W���Ȃ������B�������C�����ŏd�v�ɂȂ�͔̂ނ̉��v���̂��̂����C�ނ��X�L�s�I=�i�V�J�iScipioNasica�j��̌��V�@���d�h�ɂ���ĕs���Ȏ��𐋂����Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�C�O�͂ŐG�ꂽ�悤��imperium�ɑ���ō��̐����͂ł������u�얯�������v�́C���̍ł���u�g�̕s�N���v���N���ꂽ�Ƃ������Ƃ����ɂȂ�̂ł���B����͒�̃K�C�E�X�iGaius Sempronius Gracchus�j�̏ꍇ�����l�ł��邪���̑O133�N�̔ߌ��ȗ��Cimperium�ɑ���u�}�~�́v�͏��ł��C�����I���Q��imperium�̎��I�ω��������Ă���̂ł���B
�@�O���b�N�X���v���s��̑卬���̒��ŁC���O�h�̃}���E�X��7�x�ڂ̃R���X���ƂȂ�\�͓I�ȋ��|�������s�Ȃ����B�ނ͓�����͉��璍�ڂ��ׂ�����͍s�Ȃ�Ȃ��������C�u�}���E�X���v�v�ƌĂ��R�����v�͂₪�đ傫�ȈӖ��������Ă���B�ނ̓��O���^�푈�ƃL���u���푈�̌R���Ґ��̍ہC�����`�����s���̏��W�R�Ƃ������[�}�̕����̌������̂āC�_���̋`�������̑��ɕn���s���i�������u�s�����v�������Ȃ����̂͐��K�́u�R�c�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��j��啺�Ƃ��ĕ��Ђɉ������B����͐���Ȓ������s�\�Ȓ��x�ɂ܂Ń��[�}�s�������̂��������Ă������Ƃ���������B���Ȃ킿�C�����I��imperium��u���[�}���Ɓv�ires publica�j������ė��ׂ���Ղ����ɕ��Ă������Ƃ�������B���������āC���̎����Ȍ��imperium�����܂߂āC���[�}�̐��̂͑S���ȑO�Ƃ͈قȂ������̂Ƃ��Ĕc������K�v������B����Ȍサ�����ɋ��剻����u��W�v�iclientera�j�͂ЂƂ�imperium�̂��Ƃɒc�����Ă����u���[�}���Ɓv�ires publica�j���C�e���R�Ƃ��邢�����̃s���~�b�h�I���͊W�ɕς��C�₪�ċ��a���͑S������B
�@���a���͍����ɍ������d�ˁC�₪�ăX�b���͎���́u�얯�v�icliens�j�ō\�������R���𗦂��ă��[�}�i�R����̂���Ƃ������Ԃɂ܂Ŕ��W�����B�����Ĕނ͎����ƍي��Ɏw�������C�������imperium����ɓ���邱�ƂɂȂ������C�����Œ��ڂ������͔̂ނ�����imperium���`���I�ɂ͑S���藎���̂Ȃ��`�Ŋl�����Ă��邱�Ƃł���B����͔ނ��̂��ɗ��z���������C���E������ނ������Ƃ���������邪�C�ނ̎��_�ł͏��Ȃ��Ƃ����a���̌Â��ǂ��u���O�v�����͐����Ă����Ƃ������Ƃ������悤�B�������C����������͑����Ȃ������B
�@�|���y�C�E�X�����́C���[�}���a�������S�N�������Ēz�������Ă������a�����O�ɐ^�������痧�����������ŏ��̐l���ł������B�ނ́u�����[�}�I�s���v����Ă݂�ƁC�ނ͑S�������̌����Ŏ����R�c���������C�X�b���̃C�^���A�㗤�̍ۂɒy���Q���C�����ɃX�b���P���̈ꕔ���ƂȂ����B�������d�˂���C�S���̎��l�ł��������ĉ���@�����imperium�͎����Ă��Ȃ��̂ɂ�������炸�C���[�}�̍��ƎƂ��Ă�imperium�ێ��҂݂̂��邱�Ƃ��ł���u�叫�R�v�i�C���y���[�g�� imperator�j�̏̍��ƊM�����̉h�_���C���̂����u�̑�Ȃ�v�iMagnus�j�Ƃ����Y�����܂œ����B��̉��������[�}���ǂ͂�������F������������C�����ɍ��ƌ��E�C�R�[��imperium�ێ��҂Ƃ����C�Ō�̂����čő�̋��a�����O���ł��ӂ��ꂽ�B���̌�ɂ��|���y�C�E�X�̓q�X�p�j�A�ŃZ���g���E�X�̗��肵����C�O�㖢���̓�x�ڂ̊M���������s���C�ŏ��̌��E�Ƃ��ăR���X���E�����v�����B���a�����O�͑S���n�ɑ����B
�@���̌�̃|���y�C�E�X�̌��͐L�������Ă݂悤�B
�@�O67�N�Ƀ|���y�C�E�X�͊C�������̂��߂ɖ��\�L�̔��匠���l�������B���̓��e�́C
�@1�D�n���C����ѓ���75�L�����[�g���܂ł̌R���w����
�@2�D���B��������ʂŃv���R���X���Ɠ�����imperium��2�N�Ԃ̕ێ�
�@3�D���ɑS�̂̎��R���p��
�@4�D�l��12���l�C�D��200�ǂ܂ł̒��匠
�@5�D�v���G�g���i�̕��w�����ilegatus�j15���̔C����
�Ƃ�������Ȃ��̂ł������B�܂��C�̂��Ƀ~�g���_�e�X�푈�ɍۂ��Ă͑��B�A�V�A�i���g���R�k���j�S�̖̂����R���w�����Ə��O���Ƃ̏��������܂ł�����ɓ��ꂽ�B���̒��ŁC���ɇD�ɂ����āC�l���ɑI�����ꂽ���̂��������E�ґ��肦��Ƃ������a���������܂����݂ɂ���ꂽ�B�������C�s�v�c�Ȃ��ƂɃ|���y�C�E�X�ɂ̓��[�}�̐ꐧ�x�z�҂ɂȂ낤�Ƃ����l���͂Ȃ��C���̖��_�݂̂ɖ������Ă����悤�ł���B���̏؋��ɁC�̂��ނ͂��Ƃ���������Ƃ����̑匠��������Ă���B�����Ƃ��ނɂ͏��߂���鍑���O�Ȃǖ����悤�ŁC�����ς�l�I�h�_�����̂��߂ɋ��a�������Ă�����������B���̓_�Ń|���y�C�E�X�͗D�ꂽ�R�i�ߊ��Ƃ������Ƃ͂ł��Ă��C�D�ꂽ�����ƂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ���������Ȃ��B�ނ̔ߌ��I�Ȏ��͂������Ă���悤�Ɏv���邪�E�E�E�B�������C�l���Ă݂�C�ǂ������Ɓ��ǂ��R�i�ߊ��Ƃ���������v�̗��O�́C���z�Ƃ��Ă��܂�����������[�}���a���̖{���ł������B�����l����|���y�C�E�X�͂��̓_�ł��łɋ��a���Ƃ͑��e��Ȃ����݂ł���C�ނ���J�G�T���̕��ɂ������a���̗��O�������������Ƃ��ł���̂́C���j�̃p���h�b�N�X�ł��낤���B���̃J�G�T�����������a���𑒂邱�ƂɂȂ�̂�����B
�@�|���y�C�E�X�����Ȃ����Ȃ������C���a�����ŏI�I�ɔj���l�����K�C�E�X=�����E�X=�J�G�T���iGaius Julius Caesar�j�ł���B�|���y�C�E�X�����[�}�I�`�������C���̌o�����Ȃ��ˑR�R���X���ɏA�C�����̂ɑ��C�J�G�T���͌×�����̋M���̏o�g�ł�����C�i��i�ɖ��͂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����j�ꉞ�菇�ʂ���E�̏�����ŁC�O59�N�C�R���X���Ƃ��ă|���y�C�E�X�E�N���b�X�X�ƂƂ��ɑ�1��O���������������Ԃ��Ƃɂ���āC��[�}���E�̒��S�ɖ��o�Ă����B
�@�J�G�T����1�N�Ԃ̃R���X���E���ߏI����ƁC�܂��O���̎�茈�߂ɂ��u�A���v�X�̂����瑤�̃K���A�v�iGallia
Cisalpina�j��5�N�Ԃ̌R�w������^����ꂽ�B���ʑ��B�����̔C����1�N�B5�N�Ƃ����͈̂ٗ�̒����ł���B�������C���́u�K���A�푈�v��ʂ��ăJ�G�T���͍ŋ��̃N���G���e�[������Ă����Ă����B���ꂪ�������C�ނ̏����̌����ł������B
�@�O56�N�C�k�C�^���A�̃��J�iLuca�j�ŎO���ɂ���k���s�Ȃ��C�����Ɍ��R�ƎO�l�̓ƍق��J�n�����B
�@�K���A�푈��ʂ��Č���I�Ȓn�ʂ�z���������J�G�T���́C�N���b�X�X�̎���|���y�C�E�X��j��C����ɔ����a���I�ȓ�����g�ɂ��Ă����B�J�G�T���̓K���A�푈������C�K���A���Z���i�P���g�l����шꕔ�̃Q���}���l�j�ɑ��Ă͑S���̓ƍَ҂Ƃ��ĐU�镑���Ă������C�A�Ҍ�͑O48�E46�E45�N�̃R���X���Ƃ��č��@�I���͂āC�O45�N�ɂ͌�����10�N�Ԃ̃R���X���C�����đO49�N�H�ɂ̓f�B�N�^�g���C�O46�N������10�N�Ԃ̃f�B�N�^�g���C�O44�N�I�g�f�B�N�^�g���ƁC���X�Ɣ@�̌��͂��u���@�I�v�Ɋl�������B���̑��ɂ����I�ē��E�M���w�����E�R���P�Ǝw�����i����уC���y���[�g���̏̍��j�E���ɒP�Ɨ��p���E�M�������ƌ��j���̏펞���p�����X�C������Ȃ��قǂ̓ƍٌ��͂���ɂ���B�����͂����×���imperium�̊T�O�ł͂�������̂łȂ��C�����ɋ��a���͊��S�ɕ����ƌ�����B�������C���������������́C�܂������܂ł����a���̘g���̖�E�E�����ł���C�u���v��imperium���l�����ꍇ�[���ł��Ȃ����̂ł��Ȃ������B�������C�N�C���e�B���[�X���́u�����E�X���v�ւ̉��́C�a�����̒鍑�Փ��ւ̏��i�C�傾�����폟�L�O���̍��Əj�����C���[�}�l�̍Ղ������������ăJ�G�T���ɕ����邱�Ɓc�Ȃǂ̈�A�̑[�u�́C���܂ł̃��[�}�ɂ͑��݂��Ȃ��������Ƃł���C����͂₪�ăJ�G�T�����g�̐_�i���Ƃ����C�w���j�Y���I�ꐧ�N��T�O�ւƂȂ����Ă����B�������Cimperium�Ƃ������t�͌Â��́u���v�C�����ċ��a�����́u���E�ҁv�̌����Ƃ��ă��[�}�s���ɑI�ꂽ���ƌ��E�҂݂̂��������������S�̂ɂ��Ă̂����錾�t�ł������B�����C�J�G�T���̐_�i�����I���G���g�E�w���j�Y���I�ꐧ�N�剻�́C�S�������Ă���imperium�T�O�Ƃ͑��e��Ȃ����̂ł���B���������āC���a���̕���ƂƂ���imperium�����ł����Ƃ����Ă悢���낤�B
�@�������C�J�G�T���́C�O44�N3��15���u���[�g�D�X��̋��a��������`�҂̎�ɂ������ĈÎE����C���lj��v�͒��r���[�ɂȂ��Ă��܂��Bimperium�̍s�����̓A�E�O�X�g�D�X�̓o��������Č���Ȃ���Ȃ�܂��B
�@�O�͂ŏq�ׂ��悤�ɁC���a�������i������u�����̈ꐢ�I�v�j�̐����Ƃ�R�l�͂��͂�[�}�×���imperium�̖{���I�T�O�ɔ����邱�ƂȂ��C�Ǝ��̌����őS���َ��̌��͂�U������B������imperium�̊T�O�̓J�G�T���̐_�i���ɂƂ��Ȃ��Ď��Ƃ��������B�������C�J�G�T���̈ÎE����A���g�j�E�X�iAntonius�j�ƃI�N�^�E�B�A�k�X�iOctavianus�j�̍R�����o�āC���̔����ł��낤���C�ꎞ�I�Ɂi�����܂ł��`���I�ɂł͂��邪�j�×���imperium�̊T�O�����𐁂��Ԃ��B���ꂪ�A�E�O�X�g�D�X�iAugustus�j�̌��iPrincipatus�j�ł���C����͂₪�āu�l�ގj��ł��K���Ȏ���v�i�M�{���w���[�}�鍑���S�j�x�j�ƌ�����w���[�}�̕��a�x�ipax
Romana�j�ւƂȂ����Ă����B���āC����ł͌����̍c�錠�́C���ɃA�E�O�X�g�D�X�̂���͈�̂ǂ̂悤�ȍ\���������Ă����̂ł��낤���B
�@�J�G�T���̗{�q�ƂȂ�C���̕x�ƁC����ɏd�v�Ȃ��Ƃɂ͂��̃N���G���e�[�X�i�얯�j�������p�����I�N�^�E�B�A�k�X�́C�I���O43�N�̖���c�ɂ���āC�A���g�j�E�X�E���s�h�D�X�ƂƂ��Ɂu���ƍČ��O�l�ψ���v�Ƃ��ăJ�G�T������̍������E�ɏ��o�����B���̂�����u��2��O�������v�͔ނ̗{���̑�1��O������������߂Ď��I�Ȗ���ł������̂ɑ��C�`���I�ɂ́u���@�I�v�Ȑ����`�Ԃł������B�Ƃɂ����C�����Ŋe�ψ��ɗ^����ꂽ�����́C�����܂ł����a���I��imperium�ł������B
�@�₪�ăI�N�^�E�B�A�k�X�̓��s�h�D�X�����r�����A���g�j�E�X��j��C�v�g���}�C�I�X���G�W�v�g�����𐪕����C�{�����l���[�}�ł͕��Ԃ��̂Ȃ��n�ʂɏ��߂�B�������ނ̓J�G�T���̎��s�Ɋӂ݂āC�ꐧ�̐���ł����Ă���́i���Ȃ��Ƃ��O����́j���a����������ق�������ł���ƍl�����B�����āC�ނ�����̍�Ƃ��Ă��ݏo�������̂��u���v�ł������̂��B
�@�I�N�^�E�B�A�k�X�͖��ړI�ɂȂ����O�l�ψ����imperium���Ō�܂Ŏ�������C�O31�N����͖��N�i�ꉞ�`���ʂ�Ɂj�R���X���ɏA�C���邱�Ƃɂ����B�����ē����͌R�w�����𒆐S�Ƃ���imperium�𐳓������邽�߂Ɂu��ʓI���Ӂv�iconsensus
universorum�j�Ƃ����T�O�������o���Ă����B�ނ̌��͂͏O�l�����҂��F�߂�Ƃ��낾�Ƃ����̂��B�������C�������d�v�Ȃ��Ƃ͔ނ��O36�N�Ɍ얯�������̂����g�̕s�N���C�O30�N�ɂ͋~�ό����l���������Ƃł��낤�BIII�͂ŏq�ׂ��悤�ɁC�얯��������imperium�ɑ���C�ő傩�ō��̐����͂ł���B���ꂪ���C���Ƃ����낤�ɓ���imperium�ێ��҂̎�Ɉ����Ă��܂����B�����ɂ܂��ɋ��a�����E�҂Ƃ͑S��������C�V���ȁu���́v�̂���������܂ꂽ�̂��B�����āC���悢��O27�N������ė���B���̔N�ނ́C��2��O���������̔@�I�[�u��O28�N���������Ĕp�~���C�����̎w���������V�@�ƍ����ɕԊ҂��邱�Ƃ�\���o���B������O�̍��̌��ʂ����C���V�@�͂��̐\���o�����ۂ��C�ނɂ����˂��āu�����ҁv�i�A�E�O�X�g�D�X
Augustus�j�̏̍���i����������āu�鐭�v�̂͂��߂Ƃ����j�C���҂̑Ë��Ƃ����`�ł̂��̑��B���S�����������܂��B���Ȃ킿�C����ς݂́u���S�ȁv���B�i�A�t���J�C�M���V�A�Ȃǁj�͍����ƌ��V�@�ɁC�܂��O�G�ɂ��炳��Ă���Ӌ��⎡���̈������B�̓A�E�O�X�g�D�X�ɑ����邱�ƂƂȂ�C�ނ͑��B���Ƃ��āu�v���R���X����imperium�v�iimperium
proconsulare�j����ɂ���B�������C����͑S���̋\�Ԃł������B�܂�C�A�E�O�X�g�D�X�͔��匠�����a�����[�}�ɕԊ҂��C������@�I�Ɂu�c�鑮�B�v�́u�v���R���X����imperium�v����ɓ����B�����āC���̗��ł͔ނ͖��N�����ăR���X���ɏA�C���Ă���̂œ��R�u�R���X����imperium�v�iinperium
consulare�j��L���C�܂����V�@�c�����́u���l�ҁv�iprinceps�j�ł�����̂ŁC���V�@���B�ɂ����Ă�����߂č��@�I��imperium���s�g�������B������B�����łȂ��u���[�}�s����v�i�|�[�����E���j�����l�ł���B�������Ĕނ͑S�����a���̖@�ɂ̂��Ƃ��č��@�I�ɁC���a���̌�����������ƂȂ��C�u���[�}�鍑�v�S�̂���������C�ނ̈Ќ��̑O�ɐ��X�̖����ׂ͍����[�u�Ő���������Ă��܂����B���Ƃ��u���[�}�s����v�ł͖{�����ł���͂��́u�v���R���X����imperium�v���s��O�ł͂��ł������ł���悤�ɂ���Ȃǂ̓���I�[�u�ł���B�������C���ꂪ��̃f�B�I�N���e�B�A�k�X�́u�ꐧ�N�吭�v�idominatus�j�Ƌ�ʂ����̂́C�ЂƂ����ꂪ�A�E�O�X�g�D�X�l�̂��߂ɍl���o���ꂽ���̂ł����Č����Đ��x�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃɂ���B���Ȃ킿�C�ނ͎��������������E�����Ƃ������ƂɋN������u���Ёv�iauctritas�j�ɂ���āC���E�@�\�Ƃ͑S���ʂɌl�I�����Ƃ��Ă̏�������^�����Ă����Ƃ������Ƃł���B���������ăR���X���Ȃǂ̋��a�����ォ��̌��E�ґg�D�́C�鐭���ɂ������ď��ł͂��Ȃ������B�������C������̑[�u�͂₪�āu���x�v�ɕς���Ă����B�i���Ȃ݂Ɂu�G�W�v�g�v�̓A�E�O�X�g�D�X�Ƃ̌l�I���Y�Ƃ��ꂽ�B�j
�@�O23�N�C�A�E�O�X�g�D�X�̓R���X���E�ɗ��܂邱�Ƃ̕s����m��C��������C���邪�C���Ɋ��S�Ȍ얯�������Ɓu�㋉�v���R���X����imperium�v�iimperium
proconsulare maius�j���^�����C�O19�N�ɂ̓R���X���E�ɏA�����ƂȂ��I�g�́u�R���X����imperium�v���l�������B�����ɂ������Č��͂قڊ������邪�C���̌��͍\����������x�m�F���Ă������B�A�E�O�X�g�D�X�́u���[�}�s����v�i�|�[�����E���j�ł́u�얯�������v�ipotestas
tribunus plebis�j�Ɓu�R���X����imperium�v�ɂ���āC�����ă|�[�����E���O�ł́u�㋉�v���R���X����imperium�v�ɂ���āC���Ȃ킿�u�鍑�S�y�v�ɂ킽��x�z�����������B
�@���̑��ɔނ��тт��������Ƃ��ẮC���E�Ґ��E���C�c��ٔ����C�ݕ����s���Ȃǂ�����B
�A�E�O�X�g�D�X�̂����̌��́i��������͂�imperium�ƌĂԂ��Ƃ͂ł��Ȃ����j�͎��X�Ɓu�c��v�Ɉ����p����Ă����C���[�}�͔ɉh�̎������}����B�������C�m���̏�Ԃɒu����Ȃ����imperium�͂܂�����ł͂��Ȃ��B�ł͒N��imperium���E�������B
�@�����ɍׁX�Ƃ��̗]���𑗂��Ă���imperium���C�I��284�N�ɑ��ʂ����f�B�I�N���e�B�A�k�X�iDiocretianus�j�́u�ꐧ�N�吭�v�idominatus�j�̊J�n�ƂƂ��ɖ����Ƃ��ɂ��̐��U���I����B�������f�B�I�N���e�B�A�k�X��l�ɐӔC��ǂ킹�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ׁX�Ɩ���ۂ���imperium��3���I�̌R�l�c��̎���ɂȂ�Ƃ��̏��݂����͂�����Ƃ͂����C�������ɂ߁C���ʂƂ��ăf�B�I�N���e�B�A�k�X�̎x�z�ɍs�������B���������ăf�B�I�N���e�B�A�k�X�Ȍ�̃��[�}�c�錠�͂͂���imperium�Ƃ͌ĂׂȂ��B�������Cimperium�Ƃ̔�r�̂��߂ɂ��̊T���ɂ��ĐG��Ă݂����B
3���I�ɏo�������u�c�遁�_�v�u�c��͖@�ɂ����Ȃ��v�Ƃ������O�ɂ��C�h�~�i�[�g�D�X���̍c��́C�B��̗��@�҂ł���C�����E�����E�ٌ��Ȃǂ�ʂ��Ď���́u�@�v�����s���C�܂��C�ō��ٔ����E�����@�������Ȃǂ������Ă����B���Ɂu��l�v�i���͂�u���E�ҁv�Ƃ͌ĂׂȂ��j�̔C���E��E���������C�O���e�B�A�k�X��i367�`383�j�܂ł́u��_���v�ipontifex
maximus�j�Ƃ��āC�S�ՋV�E�Վi�̊ē����������B�����āC���ȗ��̍ō��R�w�����E�얯���������E�ݕ��������Ȃǂ��������ێ����Ă����B��������Č��Ă���ƁC���̎��Ԃ�������Ƃ���قǑ傫�ȍ��͖����悤�Ɏv����B�������C�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́C�����ɂ͌`���I�ł͂������������͑��݂����C���x�Ƃ��čc�錠�𐧌�������̂��C�ꐧ�N�吭���ɂ����Ă͑S�����ł����Ƃ������Ƃł���B�����āC�c��̃I���G���g���w���j�Y���I�_�i���́C���W���������L���X�g���Ƃ̊Ԃɋْ��W�݁C�e�����s�Ȃ��C�L���X�g���ƑË��Ȍ�̍c�錠�͂́C���Ă̐l���̓��ӂɊ�Â�imperium����C�u�_�̓��Ӂv���邢�́u�_����^����ꂽ�v���͂ւƁC���̔�������S���ʂ̂��̂ɂȂ��Ă��܂����B�������āu�Ñ�v�͖������̂ł���B
�@�O�͂܂ŁCimperium�ɂ��Ă��̋N���������܂ŁC�������ɐ����ƂƂ��Ă�imperium�ۗL�҂̗���ɗ����ďq�ׂĂ����B�{�͂ł͂�����t�ɁC�ނ炪���̂悤��imperium�����������Љ�|���̏�Ԃ͂����Ȃ���̂��������|�Ɍ��Ă�imperium�𗠑����璭�߂Ă݂����B
�@���[�}�j�Ƃ̋|��B���͂��̒����w�n���C���E�ƃ��[�}�鍑�x�i��g���X�j�̒��ŁC�u�n���C���E�v�Ƃ͒P�Ȃ�n���I�敪�⎩�R���ɂ��敪�ł͂Ȃ��C�ЂƂ̗��j�I���E�ł���ƌ����B���Ȃ킿�C���́u�n���C���E�v�ɂ́C���݂������݂��ɉe�����y�ڂ������u�ÓT�Ñ�I�|���X���s�������́v�����݂��C���̑��݂������u�n���C���E�v�̗��j�I�K�R��������Â��Ă���C���[�}���u�n���C���E�v�ꂵ�����̂��C���̎s�������̂̕����ƕ����ɂ����̂��Ɛ�������B�ȉ��C�|�펁�̋L�q�ɏ]����imperium�̑��݊�Ղł������u���[�}�s�������̣�ires
publica�j�ɂ��čl���Ă݂����B
�@�܂��C�u�����́v�Ƃ͉����H�|���̖��ɂ��ċ|�펁�́C�\�A�̗��j�w�҃V���^�G���}�����j�̐������p�����̂悤�ɐ�������B
�u�����̂Ƃ́C���j�I�Ɍ`������C�����ɕ��I�ŁC�Љ�I�ɓ����̐l�ԏW�c�ł���B���̓����Ƃ��āC�����̂́C�ЊQ�̂Ƃ��אl�ɏ��������߂錠���Ȃǂ̎Љ�I����������C�������Y�i�q���n�C�X�тȂǁj�̏W�c���p�E�����J��Ȃǂɂ��W�c�I�c�������B����ɂ���͉��炩�̓����@�\�������C�������Y�E���I���p�̓y�n�ɑ��铝�������s�g����B�����āC���ʂ��������^���e�B�������C�O���̐��E�ɑ��Ĉ�P�ʂƂ��čs������B�v
�@���Ȃ킿���ꂪ�ł��v���~�e�B���Ȍ`�ł̑��������̂ł���C����͍\���������݂��ɕ����Ȑ��E�ł������B�������C
�u���̌��n���������̂́C���I�y�n���L�E�z�ꏊ�L�E�s��Ȃǂ̔��W�ɂ��Љ�I�K�w�����ɂ���ĕ������Ă����B�����āC�₪�Ă��̕����������������̂��������ČÓT�Ñ�I�|���X�C���Ȃ킿�w�s�������́x�����܂��B�v
�@�����āC���̂悤�Ȏs�������̂́C
�u�Љ�I���W�̂��߂ɁC�₦�������𑱂��邪�C�i���ɃM���V�A�̃|���X�ɂ��̐��i���������j�u�����I�푈��ԁv�̂��߁C���̂Ȃ��Ő��������͂Ƃ��āC���q�͂Ƃ��Ă̕���j�~�́E�����͂������B�v
�@��������[�}�̏ꍇ�ɓ��Ă͂߂�C
�u�p�g���L�i�M�� patrici�j�ƃv���u�X�i����
plebs�j�̑Η��͎Љ�I�����̏؋��ł���C���[�}�Љ�͕����𑱂���s�������́ires
publica�j�ł������B�����āC����ɑ��镪��j�~�E�����͂Ƃ��Ă͌얯�����x�E������E���\�@�E���L�j�E�X=�Z�N�X�e�B�E�X�@�E�O���b�N�X�Z��̉��v�Ȃǂ��������B�������C���I�y�n���L�҂��\�H���������̏��L�n�������̂ɕԊ҂��悤�Ƃ����C���v���s�\�ƂȂ�C�Ō�̎�i�Ƃ��ĊC�O�A�������݂�悤�ɂȂ邪�C�M���V�A�̃|���X�̏ꍇ�C�A���s����s����Ɨ����C��s�Ɛ푈��ԂɊׂ�Ƃ����悤�ȐV���ȋْ��ݏo�������߁C�|���X�͕�����j�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���������[�}�͐A���s�����g���u�X�i�n��E�����j�Ɏ�荞�݁C���邢�͎s������^�����̂ŁC����̓��[�}�s�������̂̒n���I�E�l�I�ȊO���I�Ȋg��ƂȂ����B����͑��̋����̂ɉe����^���C���̕����𑣐i����B���̂悤�ɂ��Đ��������̂��w�n���C���E�x�ł���C���ꂱ�������[�}������ꂵ�������R�ł���B�v
�@�Ƃ������ƂɂȂ�B���āC���x�͂��̎s�������̂��̂Ƃ���imperium�̖����l���Ă݂悤�B
�@�u���[�}�v���u�s�������́v�ƋK�肵����Ȃ�C���̖{���ł���imperium�����̘g�̒��ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�Cimperium�Ƃ͋����̂̒��œ����҂���s���̓��ӂɂ���Đ����������\�ł���̂�����C���̎s�������̂�����Ƃ�imperium�����ł���������Ȃ��B�ݕ��o�ς̔��W�`�s��g��C�s�s�̔��W�`�K�w�����`���ނȂǂɂ�苤���̂̕������i�݁C���̑j�~�E�����͂������Ă䂭�Ƃ��C�����͂܂����[�}�s�������̂́u���l�ҁv�iprinceps�j�Ƃ��ďo�������͂��̍c�錠�͂͊��ɋ����̂��番�����C�����̂̎x����K�v�Ƃ��Ȃ��܂łɋ��剻���Ă����B�܂��C�s�������̎��̂����ɗL�����������Ă���C�c�錠�̊�Ղ́C��y�n���L�ҁE�s�s��w�Ȃǂ́u��w�K����ihonestiores�j�ł���C�u���w�K���v�ihumiliores�j�ɂƂ��čc��͐ꐧ�N��ȊO�̉��҂ł��Ȃ������B������܂���͂�u���[�}�鍑�v�ł͂�������������Ȃ����C�c�錠�͂́u�s�������́v���番�������Ƃ�imperium�ł��邱�Ƃ���߂��̂ł���B
�@�h�`VII�͂Ń��[�}��imperium�Ɋւ���l�@���I�����B�����Ŏ֑��ł͂��邪�C�Ō�Ɉꌾ�M���V�A�ɂ����錠�͂̂�����ɂ��ĐG��Ă��������B�Ƃ����̂��C�O�͂ŏq�ׂ��悤�ɁC�u�n���C���E�v�Ƃ������̂�s���̗��j�I���E�Ƃ��ĕ߂炦��ꍇ�C���[�}�ƂƂ��ɃM���V�A�ɂ��ĐG��Ȃ��͉̂旴�_���������Ǝv���邩��ł���B
�@�M���V�A�l�͂ǂ����Ă����[�}�Iimperium�̊T�O�𗝉����邱�Ƃ��ł����C������t�@�X�P�[�X����̘A�z�Łw�_�̑��x�ȂǂƖ��Ƃ����B�M���V�A�ł͑������疯�吭�������B�������C����͋ɒ[�Ȓ��ږ��吭���ł���s���̒N���������Ɍ��E�҂ɂȂ蓾���B���������āC���̌��͂��u����v�ɂ���đ傫�Ȑ������������C�G��ł�������������ł��Ȃ������B������[�}���w��i�I�x�ł������̂��낤�B�������C���ꂪ�ŏI�I�ɃM���V�A�̖��Ƃ�ɂȂ�̂�������j�Ƃ͔���Ȃ��̂ł���B�Ƃ�����C�������������R����u�M���V�A�I���́v�Ɓu���[�}�Iimperium�v�̒��ڔ�r�͍���ł���̂ŁC�����ł̓M���V�A���w�E�v�z�Ɍ����u���v�̂�����ɂ��Č������C�̂���̗�Ƃ��ăX�p���^�����ɂ��čl���Ă݂����B
�@�z�����X�́w�I�f���b�Z�C�A�x�ɂ͐������̉��i�C�^�P�[�̃I�f���b�Z�E�X�C�p�C�A�L�A�̃A���L�m�I�X��j���o�ꂷ�邪�C�ނ�͐��P���ł͂��������ƍٌ��͎͂������C�����̎҂̒��ł̑��l�҂ɉ߂����C���̍ٔ����E���J���E�ō��R���w�����Ȃǂ����Ȃ萧�����ꂽ���̂ŁC���̌�e�ՂɑI��������M�����ւƈڍs������̂ł������B
�@���ɃA���X�g�e���X�ɗ�����߂�Ɓi�w�����w�x�j�C���ɂ�5��ނ���Ƃ����B
�@�������C����5��ނ̒��ɂ����[�}��imperium�ɊY������L�ĂȌ��͂�ێ����Ă�����̂͌�������Ȃ��悤���B�܂��C�A���X�g�e���X�͉����ɂ��āC
�u���̌��Ђ͑S�Ă̐l�̎��R�ӎu�ɂ���ĔF�߂�ꂽ���̂ŁC�p�ׂ��s���ȗ��R�ɂ��Ȃ���C�l���͂����ϊv���悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�v
�u���̐�Ό��͂́C�������̐b����肷����Ă���Ƃ��������ɂ̂݊�Â��B�v
�u���͖@���ɔ����Ȃ��B�v
�ȂǂƏq�ׂĂ���B��������͑Җ]�_�ł����Ď��ۂ̂��̂ł͂Ȃ��̂ł��邪�C��Ԗڂ̂��̂��A�E�O�X�g�D�X�́u���Ёv�iauctritas�j�C�O�Ԗڂ��ꐧ�N�吭���̍c�錠�͊ςƂ悭���Ă���B
�@����ł̓M���V�A�I�����̎��Ԃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������B�X�p���^�����̗�������Ă݂悤�B�X�p���^�͐��P�������Ƃ��Ă͂������u��l�����v�Ƃ�������Ȍ`�Ԃ������C���[�}�̃R���X���Ƃ̔�r�ɂ����ċ����[���B���̌����͋����C���J�ƃG�t�H���X�̊Ď��̂��Ƃɒu���ꂽ�R�w���������݂̂ł������B������s�����C�����Ɣƍ߂Ɋւ���ٔ����͒��V�����C5���̃G�t�H���X�ƌĂ�銯���c���R�������W���C�K�͂����肵�C�w�����ւ̉������������Ă����B�ނ�͂܂������ٔ����������C���̑ߕ߂����\�ł������B������L�ĂȌ����������C���z���͖���̌����ōs�Ȃ�ꂽ�B�ЂƖڂʼn������傫�Ȑ������Ă������Ƃ�������B
�@���̂悤�ȗႩ�番���邱�Ƃ͎��̂悤�Ȉ�ʘ_�ł��낤���B���Ȃ킿�C�M���V�A�̌��͂͑����̏ꏊ�ɕ��U���C���݂������݂��������������Ă���悤�Ɍ�����B����͌Ñ㒼�ږ��吭���̗��z�Ȃ̂�������Ȃ����C������H�̌Ñ㐢�E�ɂ����Ă͑�ςɊ댯�Ȃ��Ƃł��������B���ΓI�Ɍ��āC�u���v�̃M���V�A�Ɂu���v�̃��[�}�ƕ߂��邱�Ƃ��ł������ł���B����͂��̂܂܃M���V�A�I�u������`�v�i���V���i���Y���j�ƃ��[�}�́u���p��`�v�i�v���O�}�e�B�Y���j�̍��Ƃ������Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�Ƃ������C�n���C���E�ɂ����郍�[�}�̏������Cimperium�ɂ����̂ƍl���邱�Ƃ����Ȃ��������ł͂���܂��B
�@�Q�l�����ꗗ
�i��j�N��
�i��j�E�\
II�D�e���E�҂�imperium
�R���X���i������ consul�j
�v���R���X���iproconsul�j
�f�B�N�^�g���i�ƍي� dictator�j
�C���e�����[�N�X�iinterrex�j
�v���G�g���i�@���� praetor�j
�얯���itribunus plebis�j
���̑��̌��E�҂ɂ���
III�Dimperium�̐���
IV�Dimperium�̕ώ�
�O���b�N�X�Z��
�}���E�X�ƃX�b��
�|���y�C�E�X
�J�G�T��
V�D������imperium
VI�Dimperium�̕���
VII�Dimperium�ƃ��[�}�s��������
VIII�D�M���V�A�̌��͎v�z
�i���̉��́C�R���E�ٔ��E���J�����邪�C�w�I�f���b�Z�C�A�x�̗�Ɍ�����悤�ɉ����͐�������Ă����B�j