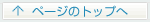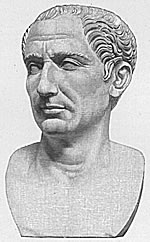ローマ史論集 - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

「ローマ人の教育について」
はじめに
紀元前1世紀、カエサルがガリアへ侵攻したとき、彼の見たものはケルト人やゲルマン人という「蛮族」であった。また、4世紀ドナウを越えてなだれこんで来たゴート族も、ローマ人にとってはやはり「蛮族」であった。しかし、なぜローマ人は彼らのことを「野蛮」と言うことができたのか?そして、なぜローマ人だけがケルトやゲルマンが為し得なかった「地中海帝国」を建設することができたのか?
話題を変えよう。なるほどギリシア人の「文化」はローマのそれをはるかに凌いだ。しかし、彼らのポリス社会は結局は衰亡せざるをえなかった。そうしてみると、ローマが強大化した原因は単なる「文化」の高低の問題ではない。その根底にあるのはローマ人特有の「ローマ文化」である。それゆえ我々は、「ローマ」について考えるとき、その「ローマ文化」形成の担い手であった「教育」の問題を避けて通るわけにはいかない。これから、その「ローマの教育」について考えてゆきたい。
第一章 初期ローマの伝統教育
(一)総説
一言で言ってしまえば、真の「ローマ教育」など存在しなかった。そこにあったのは、ギリシア=ヘレニズム教育のラテン化されたものに過ぎなかった。ギリシアのポリス(特にスパルタ)は、国家として子供の教育に責任を持った。しかし、ローマでは元来教育は個人的・家族的なものであって、何ら国家が干渉するものではなかった。それはあれほど見事な法体系を創り上げたローマが、全く文教政策に関する法律を持たなかったことからも明らかであろう。このことはまた、歴史研究にとっては致命的なことであった。史料が少ないのである。碑文史料は役に立たず、文学史料は明確さを欠く。しかし、なおかつローマの教育を研究することは、先に述べたような意味で大いに意義あることである。我々はまず、子供の目で初期ローマの伝統教育の有様を見てみよう。
(二)幼児のおかれた状態
赤ん坊は周囲の状況が目に入ると、まず自分が母親の腕に抱かれていることに気づくであろう。しかし、実は母の乳房のもとにあることができた子供は幸運であった。というのも、ローマ社会に特徴的な絶対権力を持つ家父長たる父は、その息子・娘に対して生殺与奪の権を持っていたからである。家父長は、家族の繁栄に関係のない不具の子や女の子を捨てたり殺したりする権限を持っていた。目を開くと、そこは天国・・・とまではいかなくても、拾われて奴隷部屋・・・というのは決してまれなことではなかったであろう。
さて、幸運にも家父長によって家族の一員としてとり上げられた子供は、次にどのような道を歩んだのであろうか。
ローマ人にとって、「家」(domus)は軍営であり城塞であった。そこで子供たちは、善良であることよりはむしろ規律正しい子供となることを求められた。しかし、家庭は厳しさ一点張りではなかった。家にはウェスタ(かまどの女神)のかまどに火が燃え続け、あちらにはヤヌス、こちらにはラールとペナテスと数々の神像が備え付けられ、宗教的なおごそかなムードに満ちていた。そして、何よりも子供はもの心つく頃まで母の愛情のもとで育てられ、細心の注意を払って性格形成がなされたのであった。
(三)家父長教育
さて、6〜7歳になり、もの心がつくようになると、子供は今度は父親に引き渡される。(父親がいない場合は尊敬される長老が父親の役を勤める。)そして、やがて小さな子供が農場や会議場で、時には饗宴の場でさえ、父親のあとをよちよちと、つかず離れず歩いている姿が見られるようになる。子供にとっては父親こそ「生きたローマ」であり、父親と行動をともにし、その言動を模倣することによって、我々が小学校で九九を習い、また漢字を覚えたりするように、最初の「勉強」をすることになるのである。それに対して、父親の方もまた教育には非常に熱心であった。大カトー(Cato Maior)は、子供の教育のために教科書として歴史書を一冊書き上げてしまったほどである。(ちなみにこの書物は、現在では「ラテン文学」の創始とされている。)しかし、概して父親にとって息子を教育することは、権利であると同時に、国家への献身と結びついた家父長としての義務であった。
さて、その初期教育の内容はいかなるものであったろうか。
結論から言うと、家父長教育は知的能力の発達とはほとんど無関係であった。前述の大カトーはキロンという優秀なギリシア人奴隷教師を持っていながらも、なお自分の息子の教育は自分自身で行なっていた。しかしそれは、法律・ローマ史・槍投げ・乗馬・水泳などの実用的「技術」教育のみであったといわれる。
ローマの初期教育が基本的に「家父長教育」であった理由としては、次のような理由が考えられる。すなわち、初期のローマ社会は基本的には農業を基盤とする家父長権社会であり、そこには当然家族を単位とする小共同体に基づく教育が必要であった。そのため家父長は、次の世代の、将来家父長となるべき息子を、「農業後継者」として育てることが必要であったということである。
ところで、この「父から子へ」受け継がれてゆく、農業を中心とした教育は、副産物として後のローマ史全体を貫くある理念を生んだ。それが「祖先の風習」(mos maiorum)である。このため、何か問題が起こったときには「祖先の風習」にしたがって、すなわち「今まで通り」に行なえば良いという、非常に「保守的」な「ローマ人気質」が形成されてゆくこととなった。
(四)青年教育
もの心ついてこの方、父親のあとをつき従ってきた子供たちも、やがて16〜17歳になり、トーガ=ウィリリス(大人用の上着)を着用し一人前と見なされるようになると、今度は父親のもとを離れて著名人のもとで政治雄弁術や政治技術を学んだ。これは「公生活(forum)の見習い修業」(tirocinium fori)と呼ばれ、「軍事見習い修業」(tirocinium militiae)と並んでローマ人の経歴上重要な意味を持った。
第二章 ギリシア教育とローマ教育
はじめに述べたように、真の「ローマ教育」というものは存在しなかった。しかし、なおローマはその伝統的教育理念の中にギリシアの教育とは一線を画するものを持っていた。ここではその相違について考えてみる。
ポリュビオスは「ローマ人は公教育の問題をなおざりにしている。」と言い、キケロは「我々には、法律が義務づける整った、普遍的な、いかなる公教育制度も欠けている。」と言う。すなわち、教育は公法によって監督されるべきであるというギリシアの教育理念に対して、ローマの教育は父から子へと受け継がれる、伝統・家庭生活・実例の教育であり、一言で言うならその目的は「祖先の風習」の継承であった。これは第一章で述べたとおりである。
それではここでギリシアの教育理念について触れておこう。
プラトンは『プロタゴラス』のなかで教育について触れ、子供は家庭で幼児教育を終えたあと学校へ行き、礼儀作法・音学(「音楽」ではない!)・詩・体育などを教えられるべきであるとし、さらにその後国家によって法律を教育されるべきであると説いている。またスパルタでは、子供は7歳になると母親の手から引き離され、国家の監督のもと集団生活を行ない、当然教育もその集団生活の場で受けることになった。このようにギリシア人にとっては教育とは全く「公」のものであった。そのため公立学校もアテネでは早くも前6世紀に、スパルタではさらに古くから存在していた。学校はローマにも存在はしたが、それは決して「公」のものではなく、単なる家庭教育の補助手段に過ぎなかった。それにローマでは「教師」というのは、一般に下賎な職業とされていた。
第三章 ギリシア=ヘレニズム文化のローマ流入
(一)概観
都市国家ローマは領土的拡大を続け、やがて全イタリアの支配者となる。その過程で、前4世紀にはネアポリス、前3世紀にはタレントゥムなどの「ギリシア人植民市」(Magna Graecia)を攻略した。しかし、ホラティウスが「征服されたギリシア人は猛きローマを征服した。」と言うように、これらの都市からは捕虜奴隷として多数の教育のあるギリシア人たちがローマに連れて来られ、同時にギリシア文化がローマに怒涛のごとく押し寄せることとなった。ギリシア文化流入は、ローマの東方征服によってますます拍車がかかり、やがて新たな「ギリシア=ローマ文化」が開花してゆく。
(二)ギリシア人教師
新しいギリシア=ローマ文化形成の担い手となったのは、捕虜奴隷としてローマにやって来たギリシア人たちであったが、教師として最初に讃えられるのはリウィウス=アンドロニクスであった。彼はラテン語の教科書の必要に迫られて『オデュッセイア』をラテン語に訳したが、それははからずともラテン文学の古典となった。また歴史家スウェトニウスが「半ギリシア人」(semigraeci)と呼んだ詩人エンニウスは、教師としても重要な人物であった。しかし、ローマにおけるギリシア文化興隆にとってさらに重要な人物がエンニウスの没年(前168年)にローマを訪問する。それがマロスのクラテスであった。彼はペルガモン王の使者としてローマにやって来るが、不測の事故のためしばらくローマに滞在を余儀なくされ、その間にホメロス論争等、ギリシア文学とギリシア文法についての公開講義を行なった。この講義は大好評であったが、ここに至って文法学がローマにもたらされた。続いて前155年にはアテネから使者がやって来た。当時を代表する一流の学者たち、新アカデメイア派の創始者カルネアデス、ペリパトス派学頭クリトラオス、ストア派のディオゲネスの3名である。彼らもまたローマで公開講義を行ない、非常な人気をもって迎えられた。これらのことをもって直ちにローマ人がギリシア文化を理解したとは言い難いが、とにかく大きな影響を受けたのは明らかである。
そのギリシア文化をまっ先に受容したのは、アエミリウス=パウルスとその子小スキピオらを中心とした、いわゆる「スキピオ=サークル」であった。
(三)新しい発展
ギリシア文化の流入は、第三次マケドニア戦争(前168年)以後新たな時代を迎えることとなった。ローマの圧倒的勝利に終ったこの戦争は多数のギリシア人捕虜をローマにもたらし、彼らのうち教育のある者は、ローマ人の家庭で「育児係兼家庭教師」(パエダゴーグス paedagogus)としてローマ人の精神文化形成に重要な役割を担った。彼らはローマ人の精神構造に大きな変革をもたらしたが、その代表的人物は何といっても、スキピオ家のパエダゴーグスとなったポリュビオスであろう。そしてこのスキピオ=サークルを中心に推し進められたローマの文化的発展は、まさに「前2世紀の精神革命」と呼ぶのにふさわしいものであった。大カトーのような偏屈な保守主義者もいるにはいたが、スキピオ家や教育熱心でしられるグラックス兄弟の母コルネリアなどのように、一般のローマ人はこの傾向を好ましいものと感じていた。
(四)ローマの初等教育
ローマでは、初等教育は元来家庭教育の範囲であった。しかし、それは農業生活を基盤とする社会における父子の緊密な関係を前提としていたため、ローマの領土的拡大により兵士たる父親の出征が長引き、あるいは政務に忙殺されるなどの理由で家父長権が衰退すると、当然変質せざるを得なかった。そして、その伝統的家庭教育が限界を見、崩壊したあと、父親の代役としてギリシア人教師が現われたのであった。
ローマにおける最初の初等教育機関の成立に関しては、関連法案の欠如のため時期については明確な判断を下すことができない。しかし、プルタルコスやリウィウス等の文献史料によれば、ギリシアとの接触以前にもすでにローマには学校が存在していたらしい。ローマ最初の初等学校を開いたのは前3世紀半ばのスプリウス=カルウィリウスという人物とされるが、これはどうやら初めて授業料を取った学校であり、授業料を取らない学校はそれ以前から存在していたらしい。そのような学校で教師の役を引き受けた者はクストゥス(custus)と呼ばれる、主人の家で生まれ、読み書きを修得した奴隷であった。彼らは主人の息子の従者兼保育・教育担当者として働き、やがては教師化し、ギリシア文化流入後はパエダゴーグスと呼ばれるようになる。
パエダゴーグスには三種類のものがあった。ひとつは独学した(主人の子弟の教育の場にお供して自然に教育を受けた)者たちで、このような例は数多く、最後には主人の秘書となり解放される者もあった。ふたつめは主人の利殖の対象として教育を受けた者であるが、これについては大カトーに良い例が引かれる。さて、三番めのものは捕虜奴隷等の理由でローマにやって来た教育のある者たちで、ローマの東方征服によって次第に大量の人材がもたらされた。このようにギリシア人教育奴隷(パエダゴーグス)は、安定した供給を保証され、初等教育教師の存在には困らなかった。
ローマ人の子弟は、通常7歳頃から教育らしい教育を受けることになるが、ラテン語における「教育」(educatio,動詞educare)の語は本来子供を保護監督することであって、学問教育は意味しなかった。その意味で「教育」は親の責任であり、親の代理となったパエダゴーグスも本来は子供の養育係の域を出なかった。しかし、パエダゴーグスによって始まったギリシア語教育は、やがてラテン語教育よりも優先されるようになり、バイリンギュァルであることが教養人の必須条件であると見なされるようになるに至った。
良いパエダゴーグスを獲得できれば、それは子供たちに大変良い結果をもたらすので、親たちは優秀なパエダゴーグスを優遇した。そして、そのような者たちの中には子供の教育に功績があったと認められ、解放される者もあった。彼らの中には独立して学校教師となる者もあり、時代的変遷により、個人授業よりも「学校」へ通学することが一般化していった。
一般的にはローマ人はパエダゴーグスを保護したが、それは結果として「古い」ローマ社会を崩壊させることとなった。というのは、家庭教師や学校教師はあくまでも奴隷あるいは解放奴隷であったため、社会的・政治的には最低層に属し、経済的には兼業しなければ生活できないほど不安定であった。そのため、体制側は彼らに何ら関心を示さず、何ら迫害等も行なわなかった。したがって、国家の何ら預かり知らないところで、実際の「ローマ教育」が行なわれることとなり、その教師階級が文化のイニシアティヴを握るようになったからであった。
第四章 キケロとその時代
(一)ラテン修辞学者
マリウスとスッラの時代には、ギリシア的教養、特に修辞学に対して意識的な反発があった。前92年にはラテン修辞学者追放に関するケンソル布告が出されたが、このことはギリシア文化がすっかりラテン文化と融合し、新たな「ラテン修辞学(校)」が生まれていたことを示している。このような文化的状況の中に登場したのがキケロであった。
(二)キケロ
キケロは当時随一とも言えるギリシア的教養を身につけていたが、それでも彼の教育の理念は完全な「ギリシア的教養」(パイデイア)とは異なっていた。
彼はその著書『雄弁家論』の中で教育について触れている。それによれば教育には二つのもの−「基礎的教育」(puerils institutio)と「高度の教養」(politior humanitas)−があるという。そのうち「基礎的教育」は本来は父親の教育範囲に属したものであり、のち中世の「自由学科」(artes liberales)に継承されてゆく。これは、キケロの時代には文学校や修辞学校で受ける教育内容であった。また、「高度の教養(フマニタース)」とは「教養にふさわしい学問」による教養を身につけた人間の資質であり、キケロはそのような人間を「教養のある雄弁家」(doctus orator)と呼んでいる。そして、歴史・法学・哲学などは修辞学と結びついて雄弁家のための教養と考えられた。それはとにかく、ギリシア的教養(パイデイア)とは異なる「ローマ的フマニタース」の登場であった。
第五章 ラテン文化の発展
(一)キケロ的フマニタースの発展
前43年、キケロは非業の死を遂げる。しかし、彼の遺産は次代に受け継がれ、アウグストゥスの時代にはラテン文学黄金時代が開花する。リウィウスは決して歴史だけの徒ではなく、哲学や修辞学もよくものにした。そして、ウェルギリウスの叙事詩は帝国各地の学校で盛んに教えられたのである。
(二)ローマ社会と教育の変化
地中海を「我らの海」とし、帝政が開始される頃には、かつての農業共同体としてのローマの姿はすっかり影をひそめ、かわりに大帝国が出現してくる。この社会の大きな変化が教育システムに影響を及ぼさないはずがなかった。かつての名門貴族は没落し、かわって帝国官吏としての専門職階級が台頭してくる。ローマでは従来教師・医者等の専門職は最も下賎な職業とされ、軽蔑の対象でしかなかったのだが、その彼らが勤勉と幸運によって立身出世を続けるという状況になると、特に下層階級の間で法律・医学等の専門職業教育が盛んになってきた。知識人階級は依然として修辞学を中心とする古典的「フマニタース」を重視していたようではあるが、アウグストゥスのもとでラテン文学黄金時代を迎えたのとは裏腹に、教育の方面では全分野を守備範囲とするキケロ的フマニタースは没落の一途をたどった。しかし、そのような専門教育の発展の結果、教育が帝国全土に普及したことも事実であった。(もちろん同時に従来の文法学校や修辞学校も普及した。)そして、ヒスパニア(イベリア半島)などの属州が帝国の知恵袋としてクローズ・アップされるようになるのである。ともかく、保守的貴族社会から中産職業社会へのローマ社会の変化は、実用的な教育規範を生み出し、不可避的に専門教育を発展させた。そのためであろうか、帝政期には「読み書き」のできない医者さえも存在したのである。
第六章 修辞学の勝利
これまでローマの教育を時代を追って論じてきた。そのなかでときおり修辞学についても論じてきたつもりであるが、このあたりでローマのあらゆる学芸を支配した修辞学についてまとめて整理しておきたい。
修辞学は紀元前5世紀にシチリアで発生し、やがてアテネを中心に全ギリシアに広まった。修辞学を重視したのはイソクラテスで、プラトンはそれに対して哲学重視の立場から否定的であり、アリストテレスは折衷的であったという。いずれにせよ、ソフィストらの活躍によって修辞学はアテネ民主政治の中で重要な地位を獲得する。次いでローマにもたらされ、前2世紀から前1世紀にかけて次第に他の諸学芸を圧倒してゆく。
修辞学で行なう「演説」には「法廷演説」「審議演説」「演示(練習)演説」の三種類があった。共和政盛期のローマでは三つの全てが有効に行なわれ修辞学の発展に貢献したが、帝政期になり言論・思想の自由が失われてくると、はじめの二つの演説は事実上衰退し、「練習演説」が高雅なたしなみとして幅をきかせてくる。真の古典的教育とは人間形成を目的とするものであって、専門家の育成を目指すものではなかった。その意味で人間形成の学問としての修辞学が全教養を支配するに至ったのである。哲学との闘争に打ち勝ち、最高学問として君臨した修辞学は、政治的変化に伴う雄弁術の衰退という情勢のもと、雄弁術と切り離されて中世へと受け継がれてゆく。
このような修辞学世界の中に登場してきたのがクインティリアーヌスであった。
第七章 クインティリアーヌス
(一)経歴
ローマ最高の修辞学教師であったクインティリアーヌスは、ヒスパニアで生まれ、青年時代をローマで過ごし、修辞学を学ぶとヒスパニアへ帰って修辞学教師および弁護人となった。その後再びローマへ向かい、修辞学教師と弁護人として大成功を納めた。そしてウェスパシアーヌス帝(Vespasianus,位69〜79)に認められ、執政官勲章を伴うローマ初のラテン語修辞学勅任教師となった。ここで注目すべきことは、彼の社会的地位が非常に高かったということである。元来「もし医者がいなかったら教師ほど下賎な職業はない。」といわれるほど評価の低かった教師という職業が、ここでは執政官級の名誉を与えられているのである。社会の変化に伴い、ローマの教育観も大きな変化を遂げたのであった。
(二)クインティリアーヌスの教育観
クインティリアーヌスは『雄弁家の教育』のなかで、「完全な雄弁家」こそ「良い人間」であると述べている。そこでは確かにキケロの「教養のある雄弁家」の理念は生きている。しかし、それに至る道筋にはやはり時代的な差がある。
彼は主に金持ちの子供の教育について書いている。初期教育に関しては良きパエダゴーグスを選ぶことの重要性を説き、ギリシア語教育はラテン語教育の前に行なわれるものであるべきと規定しているが、キケロと違ってギリシア語そのものに重きを置くものではなかった。また彼は学校教育を非常に重んじ、それに関してかなり詳しく述べている。その上で教師の重要性が語られ、「良い教師は子供に対して絶大な影響を与える」と、教師の人格面の資質の大切さが語られている。また、彼に至って修辞学ははっきりと最高学問として位置づけられている。「教師と修辞学の勝利」−これがクインティリアーヌス時代のローマ教育の結論であった
おわりに
合理主義に基づくギリシア的教育思想と実用主義的なローマ教育とが結び付き、ローマにおいて新しい「ギリシア=ローマ的教育」が生まれた。この新しい教育はそれまでの古代思想にカツを入れ、ローマが大帝国足りえる上での精神的・文化的基盤を形成した。しかし、その理想は次第に衰えてゆき、帝政期の文学校や修辞学校は何ら道徳的理想を持たず、またそのときその基礎となるべき市民道徳も既に存在しなくなっていた。したがって、教育そのものも帝国の消滅とともに一旦姿を消さざるをえなかった。しかし、教育は決して死ぬことはなかった。修辞学を中心とする「自由学科」の思想は脈々と生き続け、中世に至って「大学」の名のもと再び歴史の表舞台に登場してくる。しかし、その基盤はキケロでもクインティリアーヌスの思想でもなかった。キリスト教−その信仰が教育を、そして、教育の形を借りてローマを復活させたのであった。
参考文献
■ 『古典ヒューマニズムの形成』 A=グィン 著 小林雅夫 訳 創文社
■ 『ローマ人』 収録 『教育と雄弁術』 M=L=クラーク 著 長谷川博隆 訳 岩波書店
■ 『ローマの歴史』 I=モンタネッリ 著 藤沢道郎 訳 中央公論社
■ 『ギリシア人医師アスクレピアデスについて』 「史観」第104冊 小林雅夫 著