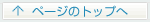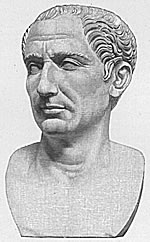ローマ史論集 - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

「ローマ法概説」
序章 なぜローマに「法」が発展したか
アッシリア・ペルシア・唐…世界史上には数多くの「大帝国」が存在する。しかし,その多くは詩人の一節に,歴史家の思い出の中に生き残っているに過ぎない。ところで,ローマ帝国の場合はどうであったか。ペルシアの権力・エジプトの富・ギリシアの英知はことごとくローマに流れ込み,消化され,やがて古代の終焉とともに幾筋もの支流となって中世・近代へと流れ出して行く。その幾多の流れの中でキリスト教と並び最大かつ最長の命を持ったものこそ,これから述べようとするローマ法であった。
実際,多くの巨大帝国が存在した中で,どうしてローマのみがあのような長期的支配を成し遂げたの か。まず,支配の要件について考えてみよう。
権力者が支配を行なうには,大きく分けて次の三つの方法がある。
1.超自然的権威で自己の支配権を正当化するもの
(オリエントの王=古代的支配者=神官,あるいは近代国家でも王権神授説をとる場合)
2.実力=正義,の軍事独裁(クーデター後の軍事政権等)
3.実力を法制度に転換して安定支配をはかる場合(ローマ帝国,近代立憲国家)
そして,この第三の場合こそローマのとった道であり,法制度の解明こそローマ支配の謎を解く鍵であ る。では,なぜそのような,いわゆる「ローマ法」がローマに生まれたのであろうか。
ローマ人の遵法精神は尊敬すべきものであった。その点,機会さえあれば法の目をかいくぐろうとする我々日本人とは大きな違いがある。ローマの人々にとって,法は「誠意」(fides) に基づいて「守るべきもの」であり,(もちろん,原則的にではあるが)裏切ることなど考えられもしないものであった。そのような彼らの法精神を基盤として,国家と市民の関係を規定する法として公法が,市民間相互の関係を規定するものとして私法が誕生してきた。そして,貴族と平民の絶ゆまぬ対立の中で公法は変化し,「古代資本主義」とまで言われる大商業帝国化の渦中で私法も発展していった。
ローマ人は優れて「常識的」な国民であった。そして,その法体系形成の上でも,その特徴はいかんなく発揮された。すなわち,彼らは,ある法制度を形成する場合,十分に詳細にわたり常識に内在するものを解き明かし,徐々にその法の中の理性的でない要素を取り除いてゆくというやり方をとった。以下の章で述べられる「ローマ法」とは,すなわちローマ人にとって守るべき「常識」であったのだろう。
第一章 ローマ法学の成立
(一)王政期の法
初期ローマにおいて,国王(rex)は,唯一無比の支配権(インペリウム imperium)をもつ国家首長であった。したがって,立法権は司法・行政権とともに王のみに属した。王は,元老院(senatus)に諮問はしたものの,ただ一人の法律提案者であり,それを最初の頃審議したクーリア(curiae)会議も貴族たち(patrici)に支配されるものであった。すなわち,この時期の法とは,ただ王と上流貴族のものであったということができる。
さて,そのような上流階級の指導のもとに種々の法が社会の要請に応じて生まれてくる。伝承によれば,ローマの建国者ロムルス王(Romulus)は結婚・子女の教育・親権に関する法を定め,立法者として名高い2代目の王ヌマ(Numa)はエゲリアの妖精と親しく交わり,その助言のもと,国際関係・宗教崇拝についての法を制定したという。そして,6代目の王セルウィウス=トゥルリウス(Servius Tullius)は市民相互の法律・契約の履行・犯罪に対する刑罰を定め,後の法学発展の基礎を築いた。以上は全て伝説によるものであり,真偽のほどは測りしれないが,だいたいこのような順序で社会の発展とともに法も発展してきたとうかがい知ることができる。
いずれにせよ,やがて王政は打倒され,共和政が開始される。王の立法権もまず貴族へ,次に平民会議決を通して平民(plebs)の手へと移行していくこととなる。そして,共和政に至り初めて「法学」の名に値する法学が登場してくるのであった。
(二)共和政初期の法学(紀元前600頃〜前202)
王政期からこの時期にかけての法は,一般に都市国家の法・農業社会の法と規定できる。
王を追放し共和政が樹立されはしたものの,それはやはり有力な少数貴族による寡頭政治であり,王の権力が貴族の手に移行したにすぎなかった。しかし,一応,王の諸権限は公職者(magistratus)に分割され,立法・司法等の権限は多く神官に委託されることとなる。神官(これもやはり貴族ではあるが)は特権階級として法知識を独占し,公法を通じて市民を支配した。しかし,やがてローマが不断の戦争状態へ突入するにつれて戦士の中軸たる中産市民層の重要性が高まり,彼らは政治意識を持ち,貴族に対して権利闘争を繰り広げるようになる。聖山事件によって護民官(tribunus plebis)という,みずからの代表を国政に送り込むことに成功した平民たちは今度は,貴族に向かって法知識の公開を迫り,ついに「十二表法」を成立させたのである。
十二表法(lex duodecim tabularum)は平民の要求によって設置された十人委員会(decemvirs)によって,前451〜450年に制定された。その内容として,第1表〜第3表には民事訴訟手続きを記し,その他重要なものとしては,家族法・相続法・後見・所有権取得(第6表),相隣権・債権法・不法行為法(第8表),その他公法・神法等について記されている。「十二表法は,全ての公・私法の源である。」(Lex duodecim tabularum est fons omnis publici privatique juris.)(リウィウス『ローマ史』)といわれるように,十二表法はローマにおける初めての制定法典であり,ローマは以後約千年間にわたり,別の制定法典を持つことはなかった。
十二表法は市民を法のもとに平等に扱おうとする意図を持ち,宗教と政策を妥協させようとするなど,貴族と平民の妥協の産物らしい性格を持ってはいたが,一事不再理の原則に基づく厳密な形式主義を貫くために,それをうまく活用するには神官団=貴族の解答・助言活動が必要不可欠であった。そのために,単純に十二表法によって法が市民全体のものになったと考えるのは誤りである。しかし,その形式を重んじながらも目的に内容を適合させようとする法学態度は,のちの法学発展を準備し,何よりもギボンが「十二表法は若い人々には暗記させられ,老年者には黙想させられた。」(『ローマ帝国衰亡史』)と言うように,ローマ国民によって大いに珍重されたのである。
前5世紀に十二表法によって法が全市民に公開されたが,それはいまだ形式的なものに過ぎず,実質的な法知識の公開は前4世紀の末を待たなければならなかった。その一つの現象が『フラーウィウスの市民法書』と呼ばれるものであった。前312年の戸口総監(censor)アッピウス=クラウディウス(Appius Claudius)の書記で,平民出身のフラーウィウス(Flavius)が法律訴訟(legis actio)の文書を盗み公開したといわれるのでこの名がある。
さらに重要なことには,身分闘争の結果として前300年には神官職(pontifex)が平民に開放され,前254年に平民初の大神官(pontifex maxmus)となったティベリウス=コルンカーニウスは,表現・文言・法発見の手続きを公開した。これによって,世俗学問としての法学(jurisprudentia)が成立したといわれる。
また,これらに次いで,セクスティウス=アエリウス(Sextius Aelius 前198年のコンスル)は俗人として初めて『アエリウスの法書』(『三部書』)を著し,「法学者の先駆」と呼ばれた。
このようにして生まれてきた世俗の学としての法学・研究的法学者の先駆者たちは,どのような性格のものであったのだろうか。
当時の先駆者的法学者たちは「行為方式」の作成(cavere)・「訴訟方式」作成助力(agere)・「法律問題への解答」(respondere)を行ない,現在の弁護士・公証人・司法書士をミックスしたような活動を通して法学を発展させていった。また,ここで神官職と法学者の区別をはっきりさせておかなければならないが,両者の活動を比較してみると,まず法の担い手としての神官は高位の公人であり,法学者は私人であった。しかし,両者ともに名望家であったということは忘れてはならない。活動形式については,両者とも無償で知識を与えたが,神官は職務として(ある程度の柔軟性は持っていたものの)唯一定まった解答を与え,それは秘儀の伝授として非公開が原則であった。それに対し,法学者は自由に見解を表明でき,その活動はその任意性ゆえに非常に活発で,その流動性・発展性は法学発展の前提となった。その点,神官は神法・祖先の遺風(mos maiorum)を維持する役割を負っていたため,どうしても保守的にならざるをえなかった。しかし,決して保守主義に凝り固まっていたのではなく,時代に適応するだけの意外に自由な法解釈の技術を身につけており,その技術は法学者の活動に大きな影響を与えた。活動の法的拘束力について言えば両者ともに持ってはいなかったが,最初に述べたようにローマ人は自発的に法に従う精神を持っていたために,神官や法学者の意見は大いに尊重された。その他,神官・法学者はともに法律問題のみを扱い事実関係は扱わなかったこと,神官の法解釈における分析的手法・抽象化作業は法学者に受け継がれていったことなどは銘記しておく必要があろう。
(三)共和政末期の法学(紀元前202〜前27)
前201年,ローマは第2次ポエニ戦争に勝利をおさめ,領土的大発展を開始する。小農業共同体が世界的大商業帝国に変化するにつれて,ローマ法も不可避的に影響を受けた。都市法から商業社会の法への変化−私法の発展がその代表的なものである。また,領土発展はヘレニズム文化との接触を引き起こし,その結果ギリシア思想がローマに流入することとなった。ギリシア思想−特に哲学と修辞学−によって実学一辺倒のローマ法学は覚醒し,法の組織的研究が始まった。定義・分類・類・固体などの概念はこの頃ローマにもたらされたものである。また修辞学は特に法廷弁論に大きな影響を与え,キケロ(Cicero)などの著名な雄弁家は法廷弁論でその名を成したのであった。さらにギリシア的自然法(jus naturale)概念や衡平(aequitas)概念は,ローマ万民法(jus gentium)の基礎となった。しかし,芸術・文学などの分野では全くギリシアの模倣に徹したローマ人も,純粋に理論的・思索的な法学研究は産み出しえなかった。彼らはやはり実学の人であった。
また,この時期のローマ法を大きく特徴づけるものとして名誉法(jus honorarium)がある。これは,公職者(特に法務官 praetor)の告示による一種の裁判習慣法であるが,詳しくは第二章で触れたい。
法学における共和政後期とは,独自の時代としてよりも古典期の準備期間としてより重要な意味を持つ。この時期において,法学に現実性・法的安定を乱さない流動性・世界法的な一般性・普遍性・信義誠実(bona fides)を基準とする解釈方法が生まれてきた。
この時期の有名な法学者としては,マニリウス(Manilius 前149年のコンスル),ユニウス=ブルートゥス(J. Brutus 前142年の法務官),プブリウス=ムキウス=スカエウォラ(P. M. Scaevora 前133年のコンスル,のち大神官)という3人の「市民法の設立者」と呼ばれる名誉法研究家,ギリシア的影響を大きく受け『市民法論』を著したクィントゥス=ムキウス=スカエウォラ(Q. M. Scaevora 前177年のコンスル),法学教育に功あったセルウィウス=スルピキウス=ルーフス(S. S. Rufus 前51年のコンスル)等があり,小カトー等「古法学者」(veteres)と呼ばれる多くの学者がいた。また,弁論家・政治家として名高いマルクス=トゥルリウス=キケロ(M. T. Cicero)は法学にも造詣が深く,ストア的哲学理論にしたがって自然法論を展開している。
ところで,法学者たちは名誉法を通して法形成に貢献したが,やがて共和政末期の内乱の時代になると法務官告示による法発展は中止し,民会の立法機能は停止してしまい,その後の法学は固定した法規範を解釈によって拡大・縮小する方向に向っていった。この事態は法学発展の可能性を内在しているものの,当時の法学者の主流が革新的な騎士階級(equites)であったこととも相関連して,法的安定性が失われるという事態につながってきた。
しかし,いずれにせよ共和政末期の法学は国家から自由なものであった。
(四)古典期前期の法学(紀元前27〜後96)
ここで言う法学の「古典期」とは,すなわち法学の「黄金時代」のことである。初代ローマ皇帝アウグストゥス(Augustus)は不安定な共和政にピリオドをうち元首政(Principatus)を開始したが,形式の上では共和政的支配を崩さず,法による支配を確立した。そのような社会の中で法学は国家権力と結合し,全盛期を迎えることになる。
この時期の法学を特徴づけるものは解答権(jus (pubulice) respondendi)の制度と,学派の対立である。解答権とは「特定の学者に付与された,解答を与えることのできる地位」のことである。その根拠は法学者の「権威」(auctoritas)の賜物で,評判の法学者は門前に列ができるほどの人気であった。しかし,この解答権を持つ法学者の解答も何ら法的拘束力を持つものではなく,一見国家(皇帝)権力から独立しているように見える。ところが,この法学者の権威は皇帝(元首 princeps)の権威の一部分であり,その意味では確かに法学と国家権力の結合が見られる。
次に,学派の対立について述べる。学派の対立はアウグストゥス帝時代からハドリアヌス帝の時代まで続いた。大ざっぱに見れば,共和主義的なプロクリアヌス(Proclianus)学派と体制派のサビーヌス(Sabinus)(あるいはカッシウスCassius)学派の対立であった学派対立は,具体的な法律問題での立場の違いによるもので,師弟関係を重視するローマ的やり方に基づいており,理論的・思想的な背景は重要ではなかった。前者に属する法学者にはラベオ,大ネルウァ,プロクルス,小ケルスス,ネラティウスらがおり,後者にはカピト(5年のコンスル),M=サビーヌス(『市民法注解』),C=ロンギーヌス(30年のコンスル),C=サビーヌス(69年のコンスル),ヤウォレーヌス,ウァレンス,トゥスリアヌス,ユリアヌスがおり,ユリアヌス(Julianus)によって学派は解消するに至った。
また,法学の方法の変化も顕著であり,ギリシア修辞学の影響により定義・概念的区別が流布し,前代の行為方式作成・訴訟方式作成助力・解答のうち,残ったのは「解答」のみであった。そして,「法学者の解答は,法を創造することを認められた者の判断および意見である。」(Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum jura candere. ガイウス『法学提要』1−7)と言われたように,法創造の上で大きな役割を果たすようになる。
(五)古典期盛期の法学(96〜193)
五賢帝のトップ・バッターとしてネルウァ帝(Nerva 位96−98)が帝位に就くのが紀元96年。このときから古典期盛期が始まり,193年セプティミウス=セウェルス(Septimius Severus 位183−211)の時代が開始されるまで続く。それは丁度,ギボンの言う「世界史上最も幸福な時代」であったが,その基盤にはやはり最高潮に達した法学の発達があったのである。
この時代の法学についてまず最初に語るべきことは,解答権の制度的完成である。すなわち,前代においては法的拘束力を持たなかった法学者の解答は,解答権を持つ法学者の意見が一致することによって法としての効力を持つことになった。この状態は,次の時代のパピニアヌス(Papinianus)の言葉によれば,「市民法は,法律・平民会決議・元老院決議・皇帝の命令・法学者の権威から生ずるものである。」(Jus civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatusuconsultis, decretis princium, auctoritate prudentium venit. 『学説集』1−1−7)といわれている。このように,法学者の学説は「学説法」として法源の一つに数えられるようになった。これは,比較法上ほとんど例を見ない,ローマ独特の制度である。 ところで,ハドリアヌス帝(Hadrianus 位117−138)は,共和政以来の顧問会(consilium)を組織化しそれに法学者を加えた。このようにして法学者は有給官僚化し,それにしたがって法学の方法自体にも変化が現われてきた。すなわち,前代の法の理論的研究は姿を消し,官吏としての実務を中心とする具体的・個別的研究(Kasuistik)に移行していったことである。さらに,この時期も終りになると,堆積した素材を秩序立て総合する著作も現われてくる。ここで,古典期法学者の研究の特徴をその作品を分類することによって総括してみよう。
1.注解−市民法注解,告示注解等
2.法学大全−ひとりの全著作,内容的に同一の著作を集めたもの
3.実際目的のための個別的研究的なもの−解答録・質疑録・討論集・書簡録等
4.入門的解説−法学提要,法範等
5.日用法書,備忘録等雑多なもの
6.特殊問題に関する著作
7.注釈
と,以上のようなものである。
さらに,この時期ハドリアヌス帝は永久告示録を作成し,ここに名誉法の発展は幕を閉じ,以後次第に勅法がその重要性を増してくる。
この時代の著名な法学者としては,ポンポニウス(Pomponius『市民法注解』『告示注解』等),ガイウス(Gaius,『法学提要』『属州告示注解』等),ユリアヌス(Julianus 顧問会会員,学派対立を終了)等がいる。
(六)古典期後期の法学(193〜284)
「永遠の都」として全盛を極めたローマに鬱りが見え始めてくるのがこの時期である。時代とともに法学も衰退せざるをえない。法学は創造力を失い,従来の素材を収録し加工する方向に移る。高名な法学者の多くは東部出身であったが決して優秀な人材に欠けていたわけではなく,最高の法学者といわれるパピニアヌス(Papinianus),ウルピアヌス(D. Ulpianus 小アジア出身),ユリウス=パウルス(J. Paulus)等の法学者が出て古典法を集大成した。また,この時期において法学者が階層化・官僚化し,騎士階級が法学者の主流を占めたことは注目に値しよう。
セウェルス朝の統治が終り,軍人皇帝の乱立する時代が始まると,政治にあまりにも密着していた法学は必然的に没落していった。
(七)古典期後の法学(284〜527)
紀元284年,ディオクレティアヌス帝(Diocletianus 位284−305)は軍人皇帝時代の混乱を収拾し,帝国を再統一して専制君主政(Dominatus)を開始する。これ以後の皇帝は筆頭市民(princeps)ではなく,まさに帝国民の「主人」(dominus)たる皇帝である。政治が変化すれば,社会も高度に発展した古代資本主義社会から現物経済の社会へと変化する。法学もまた衰退した。その原因を列挙してみよう。 1.官学化した法学を支えていた政治的安定が失われた。
2.313年の「ミラノ勅令」後,キリスト教神学が発達し,優秀な人材が神学研究に吸収された。
3.解答権が消滅し皇帝が絶対化した。
4.「法の支配」の理念が終焉した。
5.帝国の東方化により,古典法の支持基盤たる地理的背景が失われた。
等々である。
この時代は,さらに次の3つの時期に分けて考えられる。
(I)3世紀末〜ディオクレティアヌス,コンスタンティヌス帝(Constantinus 位306−337)の時期(235−337)
この時期にはまだ古典期の遺産を継承する余力が残っており,ローマ法学校は健在で法学の理論化を推進した。著作の形式としては,古典法学者(パウルス,ウルピアヌス)の著作への注解,入門書,古典期法学者の著作・勅法からの抜粋(『グレゴリウスの勅法集』『ヘルモゲニアヌスの勅法集』『ヴァチカンの断片』『モーセ法・ローマ法対照』等)の3種がある。
(II)卑俗法の時期(4世紀半〜5世紀)
卑俗法(Vulgarrecht)とは,1950年にレヴィ(E. Levy)によって提唱された新しい概念である。彼は古典法学の衰退にともない帝国の東方化・法の卑俗化が起こったとするが,法の卑俗化とはこの場合,法の素朴・単純化,具体化,情緒的なものへの変化を意味した。具体的には476年以降のゲルマン人によるローマ人法などがその例で,理論的体系を持っていた古典ローマ法は,きわめて実際的活用重視の法として使われるようになる。
(III)東ローマ法学校の時期(5世紀〜6世紀半)
東ローマ帝国には官僚養成のための二つの官立法学校があった。ベーリュートゥス(ベイルート)法学校(239年設立)とコンスタンティノープル法学校である。ここでは中世の大学にも似たやり方で法学教育が行なわれ,古典法学のような創造性は持たないものの,古典法の小ルネッサンスを現出し,6世紀の法典編纂への地ならしの役目を果たした。
この時期の法学を特徴的づけるものに,「引用法」(lex citationum)の存在がある。テオドシウス2世帝(Theodosius)とウァレンティニアヌス3世帝(Valentinianus)は426年勅法を発し,パピニアヌス,パウルス,ガイウス,ウルピアヌス,モデスティヌスおよび,その引用する法学者の学説のうち正しい引用であると確認されたものに法的拘束力を与え,学説が一致しないときには多数の説に従い,同数のときのはパピニアヌスの学説を優先し,彼の意見がないときには裁判官は意見採用の自由を持つことを定めた。学説法の発展である引用法がここに誕生し,このように勅法を通じて法の効力を付与された学説は勅法を内容とする「新法」(leges)に対して「古法」(jus)と呼ばれた。
この時期の編纂物には他に,『テオドシウス2世の勅法集』『ある古法学者の鑑定意見書』『シリア・ローマ法書(俗法)』『ローマ人法』(Leges Romanae),『アラリック法典』(Breviarium Alaricanum 西ゴート),『ブルグントのローマ人法』(Lex Romana Brugundionum),『テオドリックの告示』(Ostra-gothic Edict 東ゴート),『スイス・アルプス東部のローマ人法』(Lex Romana Criensis)。
(八)ユスティニアヌス帝時代の法学(527年〜565年)
ユスティニアヌス帝(Justinianus 位527−565)は即位するやいなや地中海周辺の旧ローマ帝国領土を再征服し,再び地中海を「われらの海」とした。帝国を旧に復し,過去の栄光を再度取り戻すことは彼の念願であり,その一環として彼は統一法典編纂を計画する。そして,法制長官トリボニアヌス(Tribonianus)とベーリュートゥス,コンスタンティノープル両法学校の教授を中心に,前5世紀の十二表法以来実に約千年ぶりに制定法典が作成された。『市民法大全』(Corpus Juris Civilis 名称は16世紀のGothefredus による)として知られる,このユスティニアヌスの法典は,当初は次の多くのものに分かれて公布された。
(1)旧勅法集(Codex Vetus)529年
(2)学説集(Digesta)530年(『会典』(Pandectae))立法のうち最も重要な成果であり,次のような内容をもつ。
1 法の概念・法源・公職者等−第1部
2 裁判について−第2部
3 物について−第3部(12〜19)
4 売買・海上消費貸借・承認・婚姻・後見等−第3部(20〜27)
5 相続財産占有等−第3部(28〜36)
6 私法・刑法・行政法等−第3部(37〜50)
(3)法学提要(Institutiones) 533年 法学校で使用する教科書−全4巻
(4)勅法集(Codex) 534年 (修正勅法,これにより1.は廃止される。ハドリアヌス〜534年までの勅法)
(5)新勅法(Novellae)535年以降(ユスティニアヌスの死(565)まで。158の法。これのみギリシア語)の勅法を後代こう呼んだ。
この法典は,あくまでも当時現行法規として作成されたものなので,古典法を現状に適合させるために修正・加筆(interpolatio)が必要であった。このinterpolatioを通して法学発展の歴史を探ることができる。
また,もうひとつ注目すべき傾向として法的ヒューマニズムがあげられる。ユスティニアヌスの立法では,家父長権制限・母子関係改善・社会的弱者の保護などが語られている。
ユスティニアヌスの法典は,ギリシア文化の影響を受けて変質した古典法であり,のち東方世界の法へと自然な発展を遂げてゆく。
ユスティニアヌス帝の『市民法大全』編纂事業ののち,『エクロガ法典』(740),『プロイケン法典』(870頃),『エパナゴガ法典』(880頃)などの小法典を経て,大法典たる『バシリカ法典』(892)が制定されるが,本格的なローマ法学の復興は中世ボローニャ大学の成立を待たなければならなかった。
第二章 ローマ法学の特質
(一)全体的特徴
ローマ法は公法と私法の二つに分かれる。公法とは国家と国民の関係を規定するものであり,私法は市民個々人の関係を規定するものであった。そして,現在「ローマ法」というと一般には私法を意味する。それは,ローマ法学が私法中心の発展を遂げてきたからであった。ローマにおいては市民個々人の権利争いの裁定は国家の義務ではなく,現在なら刑事犯として取り扱われるような事件でも,ローマでは民事事件と見なされた。そのような私法発展の基盤の上に,次に述べるような様々な原因が積み重なって私法の発展を招いた。すなわち,公法には習俗・慣行に関するものが多く法学者のレベルで取り扱うには問題があったこと,真正面から公法に取り組むことが危険視されたこと,私法においては私的自治が大幅に認られており自由な分析・解釈が可能であったこと,私法は技術的性格を強く持っていたため法学者の協力が必要であったこと等々である。また,私法及び公法思想が西欧の皇帝権力の支柱となったことは銘記されるべきである。
ローマ法のもう一つの特徴は,それが属人主義の法であるということであった。ローマ法は市民権を媒介として,理論的にはローマ市民を全く平等に扱った。しかし,やがてこの市民法(jus civile)はローマの発展にともなって変形を余儀なくされ,万民法(jus gentium)の発達を呼んだことは注目すべきことである。
(二)法曹法としてのローマ法とローマ法学
ローマ法の歴史においては,まず最初に例外的な形で法典が制定され,その後一種の判例法主義が長期間支配したが,この時期に学説法・引用法等の形成において法学者が大きな力を持ち,それが最終的にユスティニアヌスの法典につながっていった。また,法学者と実務家の区別は存在せず,理論・実践両面において法学者が法を指導した。
ところで,ローマ法が「法曹法」(Juristenrecht)であるという場合,それには二つの意味がある。一つは,ローマ法が慣習法を基盤とするゲルマン法のような「民衆法」(Volksrecht)とは異って法学者が産み出した技術的性格の強い体系を持つということであり,他の一つは,ローマ法が「法学者主導型の法」であったという意味である。前者は法学者が裁判公職者や立法者の活動を媒介とせず,直接にその実際的活動(主として解釈)や著作によって創り出した法であり,後者は法学者が他者を媒介として間接的に創りあげた法としての法曹法である。前者が解答権=学説法を,後者が名誉法を表わしているのは言うまでもない。
(三)ローマの民事訴訟手続き
法曹法としてのローマ法を考えるとき重要である二つのもののうち,解答権制度については先に第一章で述べたので,ここでは名誉法について触れる。
「名誉法は市民法の生きた声である。」(Jus honorarium est viva vox juris civilis. マルキアヌス『学説集』1−1−1−8)と言われるように,名誉法はローマ法学を考える上で重要な意味を持つが,その形成に法学者がどのように関与したかを知るには,独特の構造をもつ民事訴訟の場における彼らの役割を考察することが必要となる。
具体的に述べれば,民事訴訟手続きは法廷手続き(in jure)から始まる。これはフォルムで行なわれ,公開が原則であった。法務官(praetor)は原告(弁護人として法学者を伴う)から訴えがあると,それを法に照らして(法務官は必ずしも法に通じているとは限らないので,ここにもブレーンとして法学者が存在する)訴訟を開始するかどうかを決定する。訴訟を開始することができるなら,すなわち訴権(actio)が存在するのなら,法務官は事実認定を審判人(judex)に命ずる方式書を作成する。告訴の受理と審判人の設定は,インペリウム保有者のみが持つ重大な権限であった。(『ローマのインペリウムについて』参照)告訴に対し適当な法が存在するときには,今述べたようにことは順調に進んだ。しかし,適当な法はないけれど,常識的に考えて法で裁くべきであると考えられる場合はどうするか。法務官はそのような場合,「信義誠実」(bona fides)・「善および衡平」(bonum et aequitas)に照らして暫定的ルールとしての法務官告示(edictum)を設定したが,これは暫定的ルールにとどまらず代々の法務官に受け継がれていき,職分としての名誉(honor)が形成する法という意味で「名誉法」(jus honorarium)と呼ばれるようになった。
さて,法務官は方式書の承認という行為によって審判人を任命するとともに訴訟対象を確定し,いわゆる「争点決定」(litis contestatio)を終えて,ここで引き下がる。
法廷手続き(in jure)が終了すると,引き続き審判人手続き(aqud judicem)が開始される。審判人は現代のアメリカ合衆国などの陪審員にも似たもので,私人として選定された。この審判人(複数の場合もある)の判決は最終審であり,上訴は認められなかった。審判人は当初は元老院階層の者だけから構成されていたが,グラックス兄弟の改革時に騎士階級によって全面的に逆転されるなど,重要な任務であっただけにしばしば政治闘争に利用された。
以上述べたのは,前3世紀頃から発展してきた「方式書手続き」(per formulas agere)についての説明である。この方法は,丁度その頃からローマの訴訟に外国人が関与するようになってきたためできた方式であった。しかし,その方式書手続きも3世紀になると特別審理手続き(cognitio)に取って代わられる。これは下級官吏が一貫して訴訟を扱うものであり,方式書手続きの二分制はなくなり,国家権力が民事訴訟を完全に掌握するに至った。
ここで方式書手続き訴訟の特徴,すなわち古典期ローマの民事訴訟手続きの特徴について述べる。
まず,方式書手続きはその訴訟手続き機構の内部に法学専門家を持っていなかったため,外部より法学者の協力が必要とされた。また,手続きが二分されていることによる事実認定の複雑さによっても,法学者の協力が必要であった。私人たる審判人に説明するため,法学者からの審判人への指示は単純・明快なものであった。このことから,ローマ法の単純で明快な構成・技術性が生まれたとも考えられる。訴訟は方式書(fomula)によって決して制約は受けておらず,むしろ告示(edictum)等による柔軟性の方が特筆されるべきであろう。
(四)諸法源について
以上,名誉法についてひととおり述べた。次に名誉法以外のローマ法の法源を総括しておく。
1.法律(lex)・平民会議決(plebiscitum)
ローマにおける制定法・平民会議決で重要なものは,私法に関しては少ない。公法の場合でも,法学者が提案者の執政官や護民官を補佐した。
2.万民法(jus gentium)
実質的には,名誉法の形態をとって形成されていった。
3.元老院議決(senatus consultum)
実質的に法学者の起草によるもので,本来法的拘束力を持たぬはずだが,実際には元老院議員たちの権威(auctoritas)により絶対視された。
4.勅法(告示(edictum),訓令(mandatum),裁決(decretum),指令(rescriptum))
皇帝の出す勅法は,やがて全ての法源の上位に立つが,やはり,皇帝の名のもと法学者が形成するものであった。
(五)ローマ法の実際的性格
今まで,何度もローマ法は実際に即した法文化であると述べてきた。ここでそれを総括する。
1.ローマ法は大陸法から類推して一般に教義学的(ドグマーティッシュ)な法体系であると考えられがちであるが,実際は高度に決疑論的(カズイスティッシュ)な事例に即した法体系で,この点では大陸法よりむしろ英米法に近い。
2.『市民法大全』の中核をなす学説集は一種の判例法の集録であった。
3.『市民法大全』の法学提要はその役割上ある程度理論的に構成されてはいたが,それでも実務中心であった。
4.「市民法における全ての定義は危険である。」(Omnis definio in jure civili periculosa est. ヤウォレーヌス『学説集』50−17−202)と言われるように,法学者は個別的な事象を一般的な概念に還元したり,各事象を一定の原則によって原体的に統合することにほとんど興味を示さず,もっぱら信義誠実(bona fides)とか善および衡平(bonum et aequitas)に基づき,ケース・バイ・ケースで法を運営した。
5.ローマの法学者はあくまでも実務を重視し,法を理論的に研究する学者は後々まで現れなかった。
6.ローマ法学者の著作は『法学提要』を除いて,ほとんどが告示等に関する実際的なコメントであった。
7.ローマの法学者は,抽象的・哲学的思考方法や組織体系に関心を示さなかった。
8.ローマにおける法学教育は師弟間における法技術の伝授であり,包括的な教育計画をもった官立の法学校は古典期後の時期にようやく生まれただけである。
9.制定法典は前5世紀の『十二表法』から6世紀の『市民法大全』まで存在せず,その間一種の判例法主義が支配した。
(六)ローマ法学と国家
前節で述べたような「実学」としての法学と国家との関係とを包括的に整理するのがこの節の目的である。
一般的に法学は国家権力と結合し,御用法学に陥りやすい側面を持っている。しかし,法学史初期におけるローマはそうではなかった。法学者はそれ自体全くの私人であり,無償で奉仕活動を行なっていた。これは当然彼らが上流貴族で経済的余裕を持っていたからであるが,この国家からの中立性は後の法学の発展に大いに功あった。しかし,時がたつにしたがってこの特質は崩れてゆく。法学者の主流は共和政初期・盛期には元老院階層が占めていたけれども,共和政末期には騎士階級に移行する。帝政初期には再び元老院階層が復活するが,2世紀以後は有給の国家官吏として,騎士・東部属州出身者が台頭する。法学は出世の手段となり,国家権力に完全に従属する。
また,共和政盛期においても,上流貴族である法学者はその活動によって尊敬され,人気を得て公職者選挙で当選した。したがって,本来は私人であっても国家とかかわることとなった。
法学と国家(皇帝)権力との結合が直接的に表面化するのはアウグストゥス帝による解答権制度創設後である。解答権は,「彼の権威によって」(ex auctoritate ejus)法学者に与えられたが,それは「彼の指図で」「彼の同意によって」とも理解されうるからである。
法学者は共和政期の法務官ら公職者のブレーン,あるいはハドリアヌス帝の顧問会のメンバーとして次第に国家に接近し,やがては,皇帝に完全に従属する。「元首は法律にしばられない。」(Princeps legibus solutus est. ウルピアヌス『学説集』1−3−31)という理念は,その一つの表われであり,次いで皇帝権力を積極的に法理論化するようになってゆく。その意味でも,『市民法大全』はまったく『ユスティニアヌスの法典』であった。
第三章 ローマ法とその社会
第一章・第二章では,法をその学問としての性質を中心に扱ってきた。しかし,法というものは現代でもそうであるように法学者のみに関係するものではなく,その法の支配する社会に生きる市民全体に関係する。具体的な法制度と市民生活がどのように関係していたかを考察するのが,本章の目的である。
(一)市民・自由民・奴隷と社会
ローマにおいて「ローマ市民」(populus Romanus)は「自由人」(liber)であった。では,ローマにおける「自由」(libertas)とは一体何であったのか。
自由人たるローマ市民は2ユゲラの相続地を所有し,地租・貢租を免れていた。また自由人はラティウムの地で奴隷にされることもなく,人頭税も課されなかった。市民全体が自己の法によって生きる自由を享受していたのである。もちろん,これは初期の農業共同体としてのローマの姿であり,変化すべきものであった。
ローマ人は自らの国家を呼び表わすのに,「S.P.Q.R.」すなわち「元老院およびローマ人民」(Senatus Populusque Romanus)という呼称を使った。「ローマ人民」(Populus Romanus)というのは,理念的には唯一にして不可分のものであったが,実質は貴族(patrici)と平民(plebs)に分かれていた。前287年のホルテンシウス法(Lex Hortensia)で,平民会決議があえて「全市民」を拘束すると規定されているのはこの事実をよく物語っている。
また,自由人の内部にも様々な区別があった。自由人は大きく二分して,「生来の自由人」(ingenui)と「被解放自由人(解放奴隷)」とに分かれる。「生来の自由人」とは,自由人の両親から生まれたものであり,被解放自由人はその名のとおり奴隷の身分を解かれたものである。
解放奴隷には大まかに見て二種類がある。国家による解放と,奴隷所有者による解放とである。国家による解放とは主人の陰謀を密告した報酬として行なわれるものや,皇帝の禁令に反した主人に懲戒のために課される場合などがあった。奴隷所有者によるものは,遺言によって死後奴隷を解放するもの,生前に棍棒を使って解放するもの,戸口調査(census)のとき奴隷を自由人として登録する方法等様々なものがあった。また後には奴隷が自らを買い戻して自由を得る例があるが,これについてはのちに特有財産についての項で詳しく述べる。
いずれにせよ,奴隷は解放された後も解放者(patronus)の被護民(cliens)として留まり,積極的な自由を有するものではなかった。
また,被解放自由人にもいくつかの種類があった。十二表法には自由のみを持ち市民権を持たない,条件付き自由人のことが記されている。それはプルタルコスによれば,奴隷が国家により解放され,市民権を与えられたが最下級の市民として位置づけられたものであるという。その他,法的な区別としては「新ラテン人(ユニア=ラテン人)」と「降伏外人類」(deditici numero)とがある。「新ラテン人」とは,欠陥のある解放手続きによって解放されたが,法務官の保護によってその解放の失効を免れたものであり,自由人ではあるけれどもローマ市民ではなく,政治的な自由を持たなかった。彼らは遺言によって自らの財産を処分する権利を持たず,財産は彼の死後解放者の手に渡った。
また,純粋な「降伏外人」(deditici)とはローマ国家に従属する外人・自分の自治体を持たない外人のことであったが,「降伏外人類」とは有罪判決を受けた奴隷や格闘士奴隷が解放されたものであり,解放後も市民法の保護を受けず最低の自由身分に留まった。
次に「公有奴隷」(selvus publicus)について述べる。これは一般の奴隷と違って国家から給与を受け,一般奴隷より優遇されていた。特に「帝室奴隷」(selvus Caesaris)は皇帝側近として特別な社会的評価を受け,ティベリウス帝(Tiberius 位14−37)の側近セイヤーヌスのように,解放された後政治の実権を握る者も現われた。
さらには,「奴隷は『人』か『もの』か」という,奴隷の身分に関する問題がある。古典古代世界はおしなべて「奴隷制社会」であったといわれるが,初期農業共同体としてのローマでは,奴隷は家内奴隷として寛容な扱いを受けていた。しかし,社会発展にともない奴隷の扱いは非人道化してゆき,ついには『もの』にも劣るような扱いを受け始める。共和政末期のシチリア島(シキリア Sicilia)やスパルタクス(Spartacus)の奴隷反乱はこの状況に対する反動であった。帝政期に入ってこの状況は幾分か緩和され,ユスティニアヌス帝に至っては非常な譲歩が見られる。これは平和の連続・国力低下にともない,奴隷の供給源が枯渇したためと思われる。この事実は次のことからも証明できる。古典法においては,身分の異なるものが結婚した場合,その両者に通婚権があれば子は父の身分を継ぎ,そうでなければ母の身分を継ぐのが万民法の原則であった。しかし,ミニキウス法(Lex Minicia)やハドリアヌス帝の元老院決議等によって様々な変更が生じてくる。政府が奴隷供給源の枯渇に悩み,奴隷の生んだ子に注目していたことを示す。
市民も戦争捕虜,債務,誘拐,捨て子などによって奴隷に堕ちることがある。その際,特に問題とされるのは戦争捕虜の帰国権(postlimium)の問題である。疑問を感じざるをえないことであるが,捕虜期間中の権利(市民権)は停止され,その捕虜がある人の身代金支払いによってローマへ帰国した場合,彼は身代金支払い者の奴隷となるよう定められていた。
時代が下るにつれて,主人は損得計算やときには宗教的な理由によって,奴隷解放を頻繁に行なうようになる。奴隷制大農業(latifundium)はコロヌス制(colonatus)に取って代わられ,次第に奴隷と自由人の区別が曖昧になってくる。さらに,212年のカラカッラ帝(Caracalla)のアントニウス勅法は帝国内の全自由人にローマ市民権を与えたが,これはやがて専制君主(dominus)のもと全市民がおしなべて「低い自由」に平均化されてゆく布石となる。そして,やがて中世が訪れるのである。
(二)家族法と社会
ローマ社会は幾多の家族(familia)によって構成されていたが、それはあたかも国家内の国家のようなものであり,家族内のことに関してはかなりの自治権を持っていた。アメリカ合衆国連邦政府に対する諸州の立場を考えればある程度類推がつく。(『ローマの家父長制について』参照』
家族の長たる「家父長」(pater familias)は,妻子・家子および奴隷や道具をも含めた全家族に対して生殺与奪の大権を持った。それは家父長権(patria potestas)行使に関する紛争が,所有権訴訟と同じ形式で裁判されたことからもうかがわれる。ギボンはこのことについて「息子は家庭内にあっては父権制のもとに,単なる『もの』として扱われた。」(『ローマ帝国衰亡史』)と言っている。それは養子縁組の形式にも影響した。独立成年男子(自権者)は民会の同意を得て,新父権者の家父長権のもとに入ったが,他権者の養子縁組では旧父権者が新父権者に子を3回『もの』として売却する方法をとった。
次に婚姻について述べる。
婚姻は「同棲ではなく,合意が婚姻を作る。」(Nuptias non concubitus, sed consensus facit. ウルピアヌス『学説集』50−17−30)といわれるように,両性の合意と夫婦の愛情を基礎とするものであったが,やはり父としての家父長権・夫としての夫権(manus)と密接な関係を持っていた。
婚姻には二つの形式がある。「自由婚」と「父権帰属婚(マヌス婚)」である。自由婚は妻に対して夫の父権(manus)が成立しない婚姻で,妻は結婚後も以前の家族の家長の父権に属した。自由婚においては夫と妻は別々に財産を保有したため,女性にも物質的保証(嫁資)が確保され,女性の地位は比較的高く離婚もかなり自由に行なわれた。それでも嫁資は「他の動産と等しく,満1年の使用と所有によって夫の所有権が主張された。」(ウルピアヌス『学説集』50−17−30)という。
これに対しマヌス婚は,宗教的儀式によって結ばれ,父から夫へ嫁を売却する類似行為であった。この婚姻においては,妻は夫に対し相続等で娘の位置に(filiae loco)立つため,妻の全財産は夫に帰属した。
婚姻は本来国家から独立した私法上の行為であるが,時として国家の干渉を受けた。例をあげれば,アウグストゥス帝はユリア法(前18年),パピア=ボッパエア法(9年)で奴隷と自由人の婚姻を禁止することなどの婚姻制限立法や,男性は25〜60才,女性は20〜50才のものは婚姻の義務をもつという婚姻強制立法を行なった。しかし,これは一般に不評であった。
このような婚姻に関するローマの伝統も,やがてキリスト教の流布にともなってその宗教道徳に支配されることとなる。
家父長権に関連する重要な問題として触れなければならないものに,「特有財産」(peculium)がある。ローマの家父長社会においては家子・奴隷等が築いた財産は全て家長に帰属し,私法上の責任は家長のみが負った。初期ローマが閉鎖的な農業社会で人々が自給自足の生活をしているうちは,この制度は円滑に機能していた。しかし,商業社会が発展し家子や奴隷も支配人等として事業に責任を持つようになってくると,この伝統ははなはだ都合が悪くなってきた。なぜなら何ら固有の財産を持たず,したがって私法上の責任も持たない者が相手では,誰も安心して契約を結ぶことができなかったからである。そこで,創設されたのが「家子特有財産」である。これは家子(奴隷)に全体(家族)の中から一部の特別財産を保有させ,事業を行なわせたりその妻子を養わせたりすることを目的としたもので,家子(奴隷)はその特有財産の限度内で民事的に責任を負った。これによって取り引きの相手には安心と保証が与えられ,商業発展を一層うながした。この理念から「支配人訴訟」(船長訴訟等含む)や「分配訴権」が生まれてきたのは重要なことであり,奴隷がみずから殖やした特有財産でみずからの自由を買い戻すことがあった事実は前節で述べたとおりである。また,アウグストゥス帝は,軍務中家子が築いた財産に遺言による処分権を与え「軍陣特有財産」(peculium castlense)制度を開始したが,のち官吏である家子にも同様の権利が与えられた。(準軍陣特有財産)これらのことにより次第に家子は財産能力を承認されるようになり,やがて法的に独立してゆくことになる。
以上,ローマ社会が非常に強力な家夫長権のもとにある「家族」によって構成されていたことを述べてきた。しかし,その家夫長権も風紀取り締まり官としての戸口調査官(ケンソル censor)や帝権によって制限されたし,何よりもローマ社会が変化して「祖先の遺風」(mos maiorum)が死滅し,ローマ市民共同体が崩壊してゆくとき,家族の制度も消滅せざるをえなかった。
(三)所有権の法と社会
初期のローマ人にとって,「所有」とはまず何よりも「土地の所有」であった。彼らの正当な個人所有地とはヌマ王の土地分配による2ユゲラ(jugera)の相続地で,これは戸口調査表に記載され,地租を納める必要はなかった。これに対して借地(占有地)は戸口調査表に記載できなかった。初期ローマでは「所有」(dominium)と「占有」(possesio)ははっきりと区別されていた。土地所有の重要性は,それが何より政治・軍事的な権利基盤であったことから理解されうる。所有権を主張できるのはみずからの所有地,すなわち2ユゲラの相続地と儀式めいた「銅と秤の行為」(mancipio)によって正当に所有することになった土地のみであり,占有地はその対象にならなかった。この考えは,初期の所有権訴訟(rei vindicatio)にも受け継がれている。しかし,この場合もまた他の場合と同様に,ローマが農業共同体〜世界的商業帝国〜現物経済的官僚帝国と変化するにつれて,「所有」の概念も変化せざるをえないのであった。そして,その中で最も目につくものは「所有」と「占有」の接近・同一化である。土地の所有権に関して訴訟が起こった場合,被告はその土地の前の持ち主を召喚し,所有権を確認しようとした。その際,審判人は戸口調査表記載を(相対的に)信頼して判決を下した。これが,反対する学者も多いが「相対的所有権」と呼ばれるものである。「土地所有」の絶対的概念は崩れ去った。社会の変化にともなって所有の概念が相対化しているのがわかる。
十二表法では,土地は2年,その他のものは1年の「占有期間」を経れば,所有権訴訟においてもとの所有者より優位に立つとされた。このことから,後になって占有者は所有権を取得するとみる「使用取得」(uscapio)の概念が生まれ相対的所有権を安定させた。しかし,それに反対する措置も存在した。それが法務官プブリクス(Publicus)が設定したという「プブリキアーナ(publiciana)訴権」で,「もの」の占有をその意志によらないで喪失したときにはそれを取り戻すことができるとした。(ローマの支配領域の拡大にともない不在地主が増加し,そのため正当な所有者が知らぬ間にその土地を占有する他者が現われるという事態が起こってきた。)これを現代ローマ法学では「法務官上の所有権」という。このように「所有」の概念は次第に複雑化し,「使用」(usus) 「占有」(possesio) 「事実支配」(habere) 「所有権」(dominium)という考えの変化を経て,やがて「占有」=「所有」と考えられるようになる。(ただし,ユスティニアヌス帝のとき,この二者は再び区別されるようになる。)
この「占有」=「所有」が政治的な問題となってくるのが共和政末期の公有地占有問題であり,それこそがグラックス兄弟(Tiberius, Gaius Sempronius Gracchus)の改革の中心点であった。そして,当初たった2ユゲラだった完全な所有権を持てる私有地は,前111年の平民会決議では500ユゲラ以下の占有地となり,公有地は国が借地料を取って貸している土地で,国が買い戻し権を持ち,今後「占取」(occupatio)を許さず共同放牧地にもしない土地とされた。
さらに所有ではないが,所有権と深く係る諸権利について考えてみよう。
ローマ法においては相隣関係の規定のひとつとして,古くから他人の土地の地役権が認められていた。しかし,古典期には「役権は作為において存することができない。」といわれるように役権者側が所有者の下位に立ち,所有権の自由は絶対的性格を持ち恣意的負担から解放されていた。(すなわち,やむを得ない場合にのみ他人の土地の地役権が認められた。)さらに他人の所有物を使う権利である用役権もキケロの頃には物産の上にだけではなく,諸権利の上にも認められていた。これらの権利の拡大・発展はローマの市民の家族生活が地代・家賃・使用料・利息等に依存するものに変化したことを物語っている。
所有権の変化は担保制度の変化からもある程度追うことができるが,ローマ人は「誠意」(fides)を重視する国民で,物質による保証よりも,人(保証人)による保証を好んだ。
(四)契約法と社会
ローマ債権法はローマ法の最大の特色であり,「諾成契約」(contractus consensus)・「不当利益返還請求権」等は他のどの古代世界にも類を見ない独創的なものであった。
初期ローマの契約は「問答行為」(stipulatio)からはじまる。まさに「言語による債務関係は,問いと答から生ずる。」(Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione. ガイウス『法学提要』3−92)のである。契約には「言語契約」(contractus consensus)・「要物契約」(contractus re)・「諾成契約」(contractus consensus)・「文書契約」(chirographa)の四つがあったが,言語契約たる問答行為はその中で最も古いものである。
問答行為は契約の当事者相方が,「約束するか?」−「約束する。」という幾分儀式めいた契約を交わすものであった。これは古い素朴な法律行為で,贈与・売買・嫁資・婚約等あらゆる分野で機能した。その長所は,形式の中に様式化された社会の意志が内在し,あらゆる事例への適応が可能であるという点である。しかし,問答行為は契約する両者がそれぞれ一組の問いと答とを必要とするという二重性を持ち,どちらか一方の問答が行なわれただけでは,それは片務契約(contractus unilateralis)であるという欠点を持った。また,問答行為は文書を用いないわけだから,契約の証拠が残らない点で致命的に思える。しかし,はじめに述べたようにローマ人は遵法精神旺盛であり,いみじくもギボンが「人類および社会の信義に関する『信義の女神』は,単にその殿堂においてのみならず,ローマ人の実生活においても崇拝された。」(『ローマ帝国衰亡史 第44章)というように,信義(fides)に基づき契約を行なったようである。しかし,やがて社会が内容的にも領土的にも発展してくると,契約にも外人が絡んでくるようになる。そこで,「Aが私に負うものを君の信義に属する(fides esse)と認めるか(jubes)?」−「認める(jubeo)。」という新しい問答行為が生まれてきた。この問答行為の初期の最大の機能は保証にあった。保証は諾約者の側から見れば自由な約束であるけれども,共同体的な習俗の圧力によってなされたとも言える。同様に,司法担当公職者は古くから将来起こりうべき損害に対して表面は自由であるけれども,実は強制的に当事者の一方に対して担保(cautio)を提供させた。この担保もまた,保証人を問答行為によって要求することが多い。この問答行為を「名誉法上の問答行為」(stipulatio honoraria)という。このように信義に基づく保証の制度はローマ法制史を通じて非常に重要なものであったが,次第に保証人に負担がかかるようになり,前2世紀には保証制度の危機が現われ,保証人の負担軽減策がとられるようになる。
問答行為はその非実用性のために次第に衰え,カラカッラ帝(Caracalla 位211−217)の勅法によって文書・証書に取って代わられることになった。
つづいて売買について考えてみる。
「売買」とは商品と代価の交換であり,問答行為がなされることもあったけれども,一般には無方式の契約である諾成契約であった。初期ローマ社会はお互いを知り尽くした小共同体社会であったので,信義に基づく無方式の現物売買で事足りたのである。そして,それはまた傷のある材木を売った者はその傷の有ることを知らなくても,買い主は通常それより安い値段でそれを買うことができるのであろうから,差額を返還しなければならないというような双務性を持っていた。しかし,これも社会変化にともなって変容してくるのは当然のことであった。
「貸借」は要物契約であり,酒・金など借り主が,それと同じものが返ってくることは期待せず,ただ同じ量(額)が返ってくるのを期待する消費貸借と,馬や道具を貸した場合の当然同じものが返ってくると期待する使用貸借との二つがあった。貸借は初期社会では「貸してくれ。」−「ああ,いいよ。」式の無償行為であり,信義の支配するところであったが,やがて貸借の有償化に伴なって法に支配されるようになる。これは古い共同体が崩壊して,新しい損益計算的市民共同体が出現したことを物語っている。また,雇用契約・請負契約も賃貸借と見なされたようである。
「委任」(mandatum)は無償の契約であった。というのは,弁護人・医師・測量技師等の専門職は,「謝礼」(honorarium)は受け取ることができたが,報酬を裁判で請求することはできなかったからである。(元首政末期には特別訴訟手続きにより可能となった。)なぜなら,弁護はパトリキ貴族の道徳的義務であり,測量は神官団の固有の技術であるという具合に,それらの任務はもともと無償の好意的義務であったからである。
次に「事務管理」(negotiorum gestio)について簡単に触れておく。
事務管理はもともと解放奴隷の元の主人に対する一種の労務であり,契約には数えられなかった。敢えてここでそれに触れるのは,事務管理の任務も前述の「委任」と同様に時代が下がるにしたがって職業の社会的評価が変化し,契約の必要なものとして重要視されるようになったからである。これらは卑俗法の時代になると完全に法的強制力を持つものとなった。
何度も言うようだが,時が流れれば人も変り社会も変り法制度も変る。時代が下って卑俗法の世になると当然「契約」も変化してくる。契約は理論を捨て具体的なものとなり,原因無視・結果重視の単なる物件的譲渡行為となった。問答行為は形式を失うか消滅して証書化し,売買に関しては古典期に形成された複雑な規定・概念がなくなり,古い現実売買概念へと逆行していったのである。(「売買が締結されたときには,たとえそのものがまだ買い主に引き渡されていなかったとしても売買されたものの危険はただちに買い主に係わる。」『ユスティニアヌス帝法学提要』 3−23−3,等)
(五)犯罪・刑罰と社会
人間の存在するところ必ず犯罪が存在するし,もちろんローマも例外ではない。十二表法には死刑に相当する犯罪と,その処刑方法について次のような規定がある。
1.国家に対する反逆・敵国との通信
この国家に対する謀反を計画した者は,頭を布で覆われ,両手を背中に結びつけられ,鞭で打たれたあとフォルムで十字架に架けられた。(ローマでは不吉な木とされる,時代的にも当然キリスト教とは関係ない。)
2.ローマ市内での夜の集会
娯楽のため,宗教のため,公益のため等いかなる場合でもローマ市内における夜の集会は許されなかった。
3.ローマ市民の殺害
ローマ市民の殺害は全て死に値するが,特に毒殺は剣や短剣による殺害よりも憎むべきものとされた。また,尊属殺人は重罪で犯人は雄鶏・ヘビ・猿等とともに袋に縫い込まれて海か川へ投げ込まれた。
4.放火
笞刑ののち罪人を火に投げ込んだ。
5.裁判上の偽証罪
信義(fides)を重視したローマ人は偽証を大変嫌い,買収された証人・悪意の証人はタルペイア岩頭からさかさまに落とされた。
6.不公平な判決を宣告するために賄賂を受領した裁判官の汚職
これも5.同様,信義の問題であろう
7.公共秩序を乱す粗悪な種類の中傷文や風刺文を著作すること
これらの作者は棍棒で殴打される定めであるが,はたして死に至るまで殴打が続いたかどうかは定かでない。
8.隣人の穀物を夜間に損傷し,または破棄した罪
農業共同体であった初期ローマが農作物に対する犯罪に大きな関心を持ったのは十分に納得できる。この罪人は農業の女神ケレースへの感謝の犠牲として吊し下げられた。
9.魔術的呪文に対する罪
以上のように十二表法は非常に過酷な法であったことが分かる。その例としてよく挙げられるものに,支払い能力のない債務者に対する処罰規定がある。彼は死刑か(債権者たちに身体を分割される!)ティベリス川の向こうへ奴隷に売られたのである。しかし,一般に刑罰は軽減される方向にあり,ポルキウス法(Lex Porcia)は,法務官が自由民に対していかなる極刑も,体刑さえ課すことを禁じていた。
このように,ローマ法においてもやはり最初から犯罪と刑罰の規定があった。しかし,一般にローマ法は公法としての刑法を欠いており,窃盗さえも不当利益返還請求として民事訴訟で争われた。しかし,犯罪は野放しにしておくわけにはいかないので,公職者の懲戒権(coercitio)によって対処した。
刑法の欠如は共和政末期の混乱で痛切に感じられるようになり,スッラ(Sulla)の大量追放を皮切りに,ポンペイウス(Pompeius)やカエサル(Caesar)等によってポンペイウス法,ユリウス法などが定められ刑法が確定してゆく。さらに,帝政期になると皇帝は刑法を峻厳化し,専制支配に利用しようとした。特に「告発」の制度は最悪のもので,多くの元老院貴族が皇帝反逆罪で死に追いやられた。
もうひとつ重要なことは,帝政後期におけるキリスト教の影響がある。もともとローマは性的に寛容な国民で,オウィディウス等の詩人の作品は性的描写に満ちている。夫は,姦夫・姦婦を殺すことができたが一般に姦通は大目に見られ,共和政末期から帝政期にかけて日常茶飯事であった。しかし,ギボンの言う「触れることが嫌で仕方がないが,やむをえずさらに嫌らしい悪徳,それについて謙譲はその名をたたえることを拒絶し,自然はその概念を忌み嫌う」男色は厳格に罰せられていた。(『ローマ帝国衰亡史』ギボンは十8世紀のキリスト教イギリス人の立場からこう述べたのであり,古代ローマでも同様に考えられていたとは思われない。古典古代世界ではホモ=セクシュアリティはむしろ当然のことと考えられていた時代もあった。)ところが,キリスト教諸皇帝はモーセ法の影響を受け,姦淫・男色等性的に(キリスト教道徳に照らして)邪悪なものを殺人と同一視した。
最後にローマの刑事裁判について簡単に触れておく。
ローマ法は厳密に言えば(当初)刑法体系を欠いていたので,最初は公職者がその命令を強制するために,あるいは軽度の違反に対し罰をあたえるために「懲戒権」(coercitio)を行使した。また,公職者は比較的限られた宗教的・政治的犯罪について訴追・審問・科刑提案する権利を持ったが,ケントゥリア会議はこれに対して可否の判断を下すことができ(「民会訴訟手続」(judicium populi)),これらが事実上の刑事裁判の役を果たしていた。しかし,やがて社会が変化し,刑法が整理されてくると,裁判方法もおのずから変化する。最も特筆すべきものは「査問所手続」(quaestio)で,民事訴訟の方式書手続き中の審判人手続きに似た形態をとった。その他に,元老院メンバーによる元老院メンバーの犯罪の裁判である,「元老院審理手続」や,皇帝の下級官吏が一貫して訴訟を扱い上訴も認められる「特別審理手続」(cognitio extra ordinem)があったが,民事訴訟の場合と同じく最後には特別審理手続きに統一されてゆく。
おわりに−ローマ法と現代
ローマ帝国は滅びた。しかし,ローマ法は滅びなかった。卑俗法に堕ちたローマ法は東部ではコンスタンティノープル陥落後,バルカン諸国に細々と生き残った。しかし,ローマ古典法学を復興したのはユスティニアヌスの東部ではなく,むしろ西部であった。一旦はゲルマン法の中に埋もれたローマ法ではあったが,中世−いわゆる12世紀ルネッサンス−のもとに復活する。担い手はイタリアはボローニャ大学法学部の注釈学派であった。(その先駆者は Irnerius 11−12世紀, Bulgarus, Martinus, Hugo, Jacobus)彼らの復興した古典ローマ法は分裂・混乱を続けるヨーロッパの中でキリスト教とともに数少ない統一的理念となり現代に至っている。ドイツ,すなわち神聖「ローマ」帝国は,15世紀にローマ法を全面的に「継承」(Rezeption)し,それは1900年のドイツ民法に受け継がれる。そして,ドイツ民法はオーストリア(1811),スイス(1911),日本(1898),ロシア(1924),中国(1926),ハンガリー(1928),チェコスロヴァキア及びユーゴスラヴィア(1920),ポーランド(1933),リトアニア(1937),タイ(1925),ギリシア(1940,それ以前は完全なローマ法),ブラジル(1916),メキシコ(1928),ペルー(1936),その他,トルコ,リヒテンシュタイン,イタリア等世界中の国に広がっていった。我々日本人でさえ,幾分かは二千年の昔にトーガをまとった人々が創った法のもとに生きているのである。このドイツ民法系の法とフランス系の法がいわゆる「大陸法」(Civil Law)で,「普通法」(Common Law)である英米法と区別される。したがって,英米法は直接にはローマ法と関係ない。しかし,その法技術においてローマ法の恵みを受けていることは否定できない。
現在でもオランダ系ローマ法をそのまま使用している南アフリカ共和国のような特殊な場合を除けば,ローマ法と現代は直接の関係を持たないのかもしれない。しかし,我々は今でもローマ法から法的技術・法的思考のパターンを学ぶことができるし,何よりも博物館に入ってしまった多くの古代文物とは違い,今でもローマ法は我々の上に生き続けているのである。
参考文献一覧
■ 『法学史』(ローマ法の章) 柴田光蔵 著 東京大学出版会
■ 『ローマ法の基礎知識』 柴田光蔵 著 有斐閣双書
■ 『ローマ法−現代に受け継がれるローマの遺産』 柴田光蔵 著 聖文社『受験の世界史』1978年4月号 収録
■ 『ローマ法学の成立』 吉野悟 著 岩波世界歴史講座3 収録
■ 『ローマ法とその社会』 吉野悟 著 近藤出版社 世界史研究双書
■ 『ローマ法学の理念』(『ローマ帝国衰亡史』第44章)エドワード=ギボン 著 戸倉廣 訳 有信堂
■ 『ローマ人』(第6章『ローマ法』) E=H=ローソン 著 長谷川博隆 訳 岩波書店
■ 『ローマ帝国の国家と社会』 弓削達 著 岩波書店
■ 『ローマ帝国と地中海世界』 弓削達 著 岩波書店
■ 『ローマ人の国家と国家思想』 E=マイヤー 著 鈴木一州 訳 岩波書店
■ 『カエサル」 長谷川博隆 訳・編 平凡社 世界を創った人々(2)
■ 『古典ヒューマニズムの形成−キケロからクインティリアヌスまでのローマ教育』 A=グィン 著 小林雅夫 訳 創文社 歴史学叢書
■ 『ローマの歴史』 I=モンタネッリ 著 藤沢道郎 訳 中央公論社
■ 『ローマ帝国衰亡史』(皇帝在位年表) ウォールバンク 著 吉村忠典 訳 岩波書店
■ 『物語・ローマ建国神話』 ガイ=ド=トーリーヌ 著 植田・大久保 訳 社会思想社教養文庫
■ 『古代ローマ・風俗文化史』 オットー=キファー 著 大場正史 訳 桃源社
■ 『年代記』 タキトゥス 著 国原吉之助 訳 岩波文庫